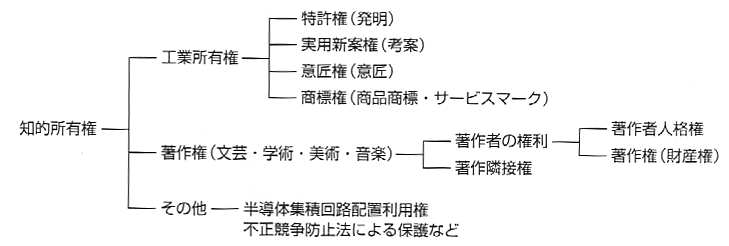
10-1 知的所有権とは
国連の専門機関である世界知的所有権機関(WIPO)の設立条約第2条では、知的所有権を「文芸・美術および学術の著作物、実演家の実演・レコードおよび放送、人間の活動のすべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービスマークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業・学術・文芸または美術の分野における知的活動から生じる他のすべての権利」と定めている。
「知的所有権」は「Intellectual Property Rights」の訳語であるが、「所有権」という語のもつ法律的概念と必ずしも一致しないということで、現在、「知的財産権」という語も同じ意味で使用されている。
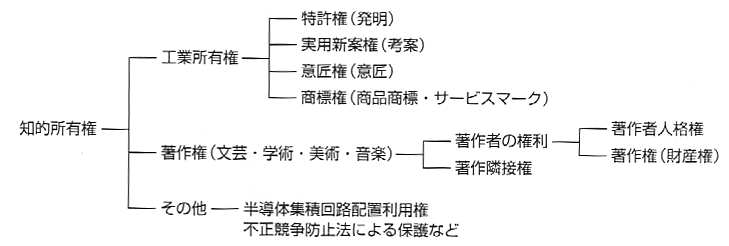
10-1-2 著作権法の目的
著作権法第1条にはにの法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関して著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と規定している。すなわち著作権制度は、著作者と著作隣接権者の経済的、人格的な利益を保護することによって創作を促し、その結果よりすぐれた著作物が生まれることで、最終的には「文化の発展に寄与する」ことを目的としているのである。
以下において、著作物、著作者、権利の内容、著作権の制限(公正な利用)などについて順次解説する。
人間の知的創作活動などから生産された知的財産として著作権法上保護の対象となるものが「著作物」であり、その用語の意味は次のように定められている。
10-2-1 著作物とその種類
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(第2条1項1号)と定義されている。したがって、思想、感情を表したものでない単なる事実(データなど)を並べただけのものは著作物とはいえない。著作物は、創作性を有することが重要な要素であり、その学術性、芸術性、新規性については問題とされていない。さらに著作物は、その表現形式や完成のいかんに関係なく、創作的個性が客観的に外部に表現されたもののみが保護の対象となるので、著作者の内心にあって他人には知ることができないようなアイデアは保護されないと解されている。また、文芸、学術、美術、音楽の範囲とは個別に分類されるものではなく、知的・文化的包括概念の範囲とされている。
著作権法は第10条1項で著作物を表現形態別に例示しているが、例示に含まれなくとも上記の著作物の定義に属するかぎり著作物と認められる(表10.1)。
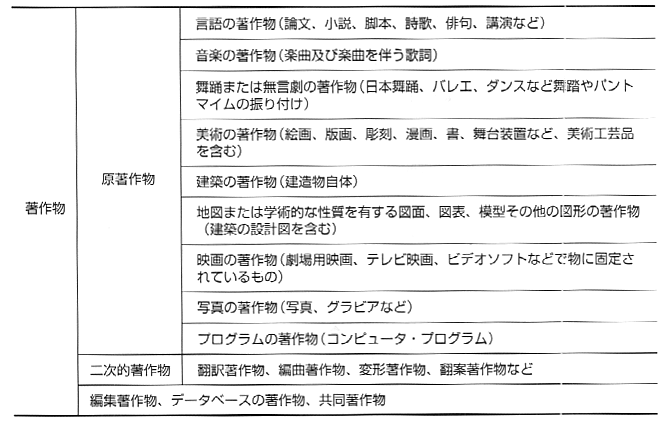
10-2-2 原著作物と二次的著作物
著作物を基礎として新たな著作物を創作する場合、その基礎となる著作物を原著作物という。また、原著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することにより創作した著作物を二次的著作物という(第2条1項11号)。二次的著作物を創作する場合は、原著作物の著作者の許諾が必要である。また、二次的著作物を利用する場合は、二次的著作物の著作者とその原著作物の著作者両者の許諾が必要である。
●他人の作品を利用しても二次的著作物とはいえない場合
A著作物を利用してA著作物とは全く別のB著作物が作成され、B著作物からA著作物の存在を感得できない場合は、B著作物はA著作物の二次的著作物とはいえない。したがって、Bの作者はA著作物を利用するにあたり、Aの著作権者の許諾を得る必要はない。
10-2-3 美術の著作物
絵画、書などの場合、その作品自体は著作物であるが、画風、書風などの流儀は著作物にはならない。したがって、作風の模倣は盗用とは異なる。また、表現の手段として用いるものは紙、木板、金属板、雪など何であってもかまわないので、コンピュータグラフィックス(CG)作品の場合、画面上の表現も保護される。
10-2-4 映画の著作物
映画とは思想または感情を影像の連続によって表現する著作物をいう。映画および映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物とされている(第2条3項)。なお、映画の一部であるワンカットなどは影像の連続ではないので、映画の著作物ではなく写真の著作物に含まれる。
●ビデオゲームを「映画の著作物」に該当するとした判例
東京地裁昭和59年9月28日判決の損害賠償請求事件の判決において、ビデオゲーム「パックマン」は、影像が連続的に変化しているように見せる方法で表現されているものであるから、映画の効果に類似する視覚的効果を生じさせROMに固定されているといえるので映画の著作物であると認め、海賊版のビデオゲーム機を、無断複製品であることを過失により知らずに購入し、自己の喫茶店に設置し上映することは、映画の著作物の上映権を侵害するとした。また、同じく「パックマン」に関する東京地裁平成6年1月31日判決の著作権侵害差止等請求事件において、ビデオゲーム「パックマン」が映画の著作物に該当し、「パックマン」に極めて類似し、かつ、フリーウェアまたはシェアウェアとしてパソコン通信で流布していた第三者作成のパソコン用ゲームのプログラムを、ゲーム解説を内容とする書籍の付属ディスクに収納して書籍とともに販売した行為が、「パックマン」の複製権、頒布権、同一性保持権および氏名表示権を侵害するとした。
10-2-5 プログラムの著作物
コンピュータプログラムは1985年(昭和60年)の著作権法の改正によって著作物として保護することが明確になった。プログラムは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(第2条1項10の2)と定義され、著作物の例示に加えられた。しかし、プログラムを作成するために用いる「プログラム言語」「規約」「解法」は保護されない(第10条3項)。また、プログラム著作物の性質上、特定のコンピュータで利用するための改変およびデバッグやバージョンアップなど必要な改変(第20条2項3号)や、バックアップコピーなどプログラム所有者による自らの利用において必要な複製、翻案(第47条の2)は認められている。さらに、違法コピーであることを承知の上で取得したプログラムを業務上使用する場合は、著作権侵害行為とみなされる(第113条2項)。
権利の発生とは関係ないが、権利をよりじゅうぶんに保護するために設けられた著作権登録制度がある。とくにプログラム著作物の場合は、創作後6か月以内に創作年月日の登録を行うことができる(第76条の2)。プログラムの登録手続きは文化庁長官指定の登録機関である財団法人ソフトウェア情報センターが行っている。
10-2-6 編集著作物
百科事典や雑誌、あるいは新聞など編集物で素材の選択または配列によって創作性を有するものは、そこに収録されている個々の著作物とは別に編集著作物として保護される(第12条)。編集著作物の権利が及ぶのは、それをその編集物として利用する場合のみである。したがって、編集著作物全体および一定のまとまりのある部分を複製する場合は、収録されている個々の著作物の著作者と編集者の両者の許諾が必要である。新聞の場合、紙面1ページは編集著作物の一部として創作的成果が認められるかぎり、編集著作物の権利が及ぶとされている。
10-2-7 データベースの著作物
データベースは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」(第2条1項10号の3)と定義されている。情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するデータベースは、データベースの著作物として保護される(第12条の2)。したがって、データベースを一定のまとまりでダウンロードしたり、プリントアウトすることは、データベースの著作権者の許諾を受けなければならない。
データベースを作成する場合、素材としての個々の情報の著作物については、編集著作物と同様にその利用に関して個々の著作物の著作権者の許諾が必要である。しかし、文献データなどのアブストラクト(抄録)や要旨としての利用の場合は、著作物の翻案に該当しないので許諾を得る必要はないとされている。ただし、要約の場合は翻案に該当し許諾が必要となるので、注意する必要がある。
10-2-8 保護されない著作物
次に該当する著作物は保護の対象とならないとされている(第13条)。
①憲法その他の法令
②国または地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達など
③裁判所の判例、決定、命令および審判など
④上の①から③の翻訳物および編集物で、国または地方公共団体の機関が作成するもの
10-2-9 マルチメディア・ソフトの著作物
マルチメディアで利用されるソフトが「マルチメディア・ソフト」であり、マルチメディア・ソフトも著作権法卜著作物の定義に該当するかぎり著作物として保護される。なお、このマルチメディア・ソフトを、メディアの統合とインタラクティブ性からとらえた「マルチメディア・ソフトの著作物」として新たなカテゴリーを設けるか否かについて、現在、文化庁の著作権審議会マルチメディア小委員会で検討中である。
しかし、CD-ROMなどのパッケージ型ソフト(マルチメディア・タイトル)などについては、その種類、性質に応じて現行著作権法で例示するデータベースの著作物、編集著作物、映画の著作物、プログラムの著作物(マルチメディア・タイトルを作成し運用するためのオーサリングソフトなど)として保護することが可能である。また、CGによって制作されたものは、その種類に応じて美術の著作物、図形の著作物、映画の著作物に該当すると考えられる。
なお、マルチメディア・タイトルに音楽を使用したり、俳優を起用したり、声優によるせりふを入れる場合などには、それぞれ音楽の著作物としての保護や、俳優、歌手、演奏家、声優など実演家の著作隣接権の保護を考慮する必要がある。
※「マルチメディア・ソフト」「マルチメディア・ソフトの著作物」「マルチメディア・タイトル」の用語は、著作権審議会マルチメディア小委員会第一次報告書(平成5年11月)で使用されているものを用いた。現在、パッケージ型、通信ネットワーク型を問わずマルチメディアで利用される情報内容を「コンテンツ」「デジタル・コンテンツ」「マルチメディア・コンテンツ」などとよんでいるが、各用語の定義は一定していない。
著作者とは、著作物を実際に創作した者である(第2条1項2号)。原則的には著作者が、著作権の帰属主体である著作権者となる。しかし、譲渡や相続などによって著作権の移転が行われた場合は、著作者以外の者が著作権者となることがある。さらに、特殊な場合として以下の3つの著作者があげられる。
10-3-1 共同著作物の著作者
2人以上の者が共同して創作し、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができない共同著作物(第2条1項12号)の著作者を共同著作者という。その著作権は、共同著作者の共有となり、共有著作権の行使は、その共有者全員の合意によらなければならない(第65条2項)。
10-3-2 法人著作・職務著作
職務上作成される著作物の著作者は、次の要件をすべて満たせば会社など法人が著作者となる
(第15条1項)。
①法人その他の使用者の発意に基づくものであること
②法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
③法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること(プログラムの著作物を除く)
④作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
プログラムの著作物の場合は、プログラムが公表されずに利用されることが多いので上記③の
要件が削除され、名義のいかんを問わず、公表されなくても①②④の要件を満たせば法人著作と
認められ、著作者はその法人となる(第15条2項)。
●著作者の判断と留意点
A社がBデザイン会社に作品を依頼し、B社の社員Cと外部のデザイナDが中心的に作品創作にあたった場合、完成作品の著作者は誰になるか?
A社は、依頼者でありスポンサであって、著作者ではない。
B社の社員Cの創作による完成作品は、法人著作の要件が全部満たされる場合法人著作となり、B社は著作者となる。
社員Cは、B社の従業員であるから、実際に創作した場合でも別段の定めがなければ個人的には著作者とはなれない。
デザイナDについては、基本的には作品制作業務におけるB社との契約関係に依存する。たんなる契約社員の場合は著作者とはなれないが、そうでない場合は、創作における寄与分によりB社と共同著作者となることが考えられる。また、B社がDに全面的に創作を依頼し、社員Cが補助的な作業をしたに過ぎない場合は、実質的に創作行為をしたDが著作者となる。
A社は、最終的な完成作品の著作権がA社に帰属する旨を契約で明確にしておけば、著作権者となることができる。したがって、トラブルを避けるためにも、制作の時点で、完成作品の著作権の帰属先や作品の使用範囲などを当事者間で契約によって明文化しておくことが望ましい。
10-3-3 映画の著作物の著作者・著作権者
映画の著作物は、著作者と著作権者が著作権法上はじめから分離している。映画の著作物の著作者は、法人著作に該当する場合を除き、制作、監督、演出、撮影、美術などを担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とされ、その原作の小説家、脚本家、音楽家などは除かれる(第16条)。俳優は実演家として著作隣接権による保護を受ける。そして映画の著作物の著作権は、映画著作物の著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する(第29条1項)と特例が定められている。ここでいう映画製作者とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(第2条1項10号)である映画会社や制作プロダクションに該当する。したがって映画著作物の場合、著作者である監督らが著作者人格権を、著作権者である映画製作者が著作財産権を取得することになる。しかし、このような権利帰属規定は、もともと劇場用映画を想定したものであるので、今日の映画製作の実態、映画の種類や利用方法の多様化などを考慮すると、著作者や実演家などの利益がじゅうぶんに保障されていないという問題が指摘されている。
10-4 権利の内容
著作者の権利には、財産的利益を保護する著作権(著作財産権)と、人格的利益を保護する著作者人格権の二種類がある。他人が著作物を利用する場合は、原則としてその利用行為に対する著作権者の「許諾」が必要である。したがって、無許諾で他人の著作物を正当な理由なく利用する場合は、これら著作権の侵害となる(「10-5著作権の制限」参照)。
10-4-1 著作者の権利
著作者人格権と著作権(著作財産権)は、著作者が創作した時点で自動的に発生し、いかなる方式や手続きも不要(無方式主義)である(第17条2項)。これは出願・登録などの手続きが必要(方式主義)な工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)とは異なる(表10.2)。
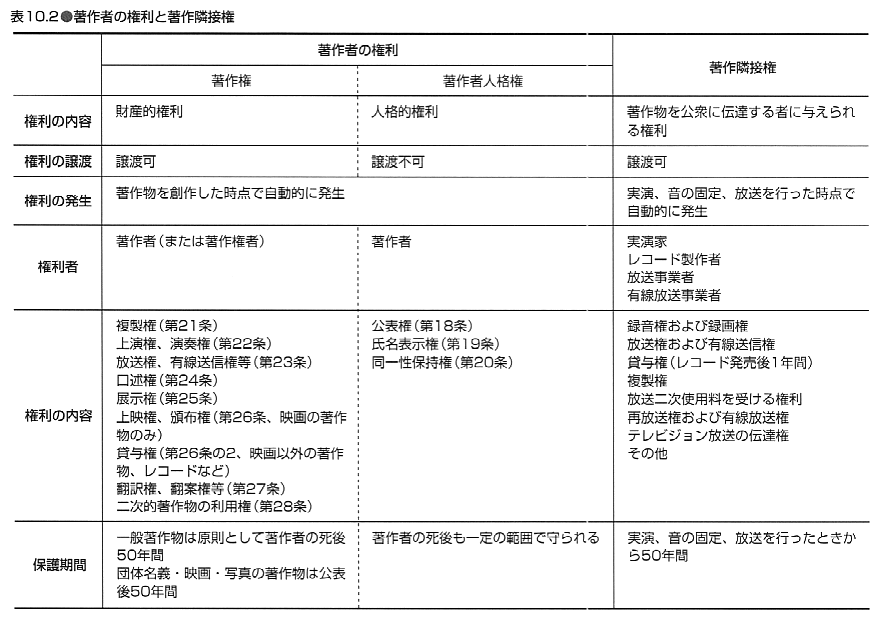
[1]著作権(著作財産権)
著作権は複製権を基本とし、著作物の利用形態に応じたさまざまな支分権の束である。複製とは、印刷、写真、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(第2条1項15号)で、この著作物の有形的利用権としての複製権はすべての著作物が有する基本的な権利である。その他の上演・演奏、放送、口述、展示、上映などの無形的利用権は、「公に」と定義され、公衆(特定かつ多数の者を含む)を対象とする行為に限り権利が及ぶとされている。著作権(著作財産権)は全部または一部を譲渡することができる(第61条)。
[2]著作者人格権
著作者人格権に属する公表権(第18条)は、未公表の自分の著作物を公表するかしないかを決定する権利、氏名表示権(第19条)は自分の著作物を公表するときに著作者名を表示するかしないか、表示する場合は実名か変名かを決定する権利、同一性保持権(第20条)は、著作物の性質ならびにその利用目的と利用の形態に照らしてやむを得ないと認められる場合などを除き、自分の著作物の内容、題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利である。著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない(第59条)。
●著作物の偶然の一致は著作権侵害とならない
新しく作成されたB著作物が既存のA著作物と同一または類似であった場合、Bの作者がA著作物の存在、内容をまったく知らずに独自にBを創作したのであれば、Bの作者の行為は著作権侵害にはならない。これは、著作権と発明、意匠などの工業所有権との大きな違いである。工業所有権は、先に登録済みの特許発明、登録意匠などが二個以上存在することはありえず、その内容、存在を知らなかった場合でも同一または類似のものを実施すれば侵害行為となる。
音楽の著作物に関する「ワン・レ二一・ナイト・イン・トーキョー事件」(最高裁昭和53年9月7日判決)において、最高裁は、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは」著作物を複製したことにはならないとし、既存の著作物の「存在、内容を知らなかった者は、これを知らなかったことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない」と判示した。
10-4-2 著作隣接権
著作隣接権は、著作物を創作する者ではないが、著作物を一般公衆に伝達する役割を果たしている実演家(俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利である(第89条)。
10-5-1 著作物の自由利用
下に示すような場合には、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができる。ただし、複製・利用の形態に応じて著作物の出所の明示をする必要があり(第48条)、これら規定の適用を受けて作成された複製物の目的以外に使用することは禁止されている(第49条)。さらに、著作権(著作財産権)が制限され第三者が著作物を自由に利用できる場合でも、著作者人格権は制限されないので、著作者人格権を侵害する形で著作物を利用することはできない(第50条)。
なお、これら著作物の自由利用が可能な場合でも利用方法は限定されているので、拡大解釈することによって著作権者の利益を不当に害さないよう、また著作物の通常の利用が妨げられることのないようじゅうぶん注意する必要がある。
著作物が自由に使える場合
①私的使用のための複製(第30条)
②図書館などにおける複製(第31条)
③引用(第32条)
④教科用図書などへの掲載(第33条)
⑤学校教育番組の放送など(第34条)
⑥学校その他の教育機関における複製(第35条)
⑦試験問題としての複製(第36条)
⑧点字による複製など(第37条)
⑨営利を日的としない上演など(第38条)
⑩時事問題に関する論説の転載など(第39条)
⑪政治上の演説などの利用(第40条)
⑫時事の事件の報道のための利用(第41条)
⑬裁判手続などにおける複製(第42条)
⑭放送事業者などによる一時的固定(第44条)
⑮美術の著作物などの原作品の所有者による展示(第45条)
⑯公開の美術の著作物などの利用(第46条)
⑰美術の著作物などの展示に伴う複製(第47条)
⑱プログラムの著作物の複製物の所有者による複製など(第47条の2)
10-5-2 私的録音録画補償金制度
平成5年6月1日から、私的録音録画補償金制度が実施された。従来、家庭内などで私的に使用する場合は著作物を自由に無償で複製することができたが、デジタル方式の録音録画機器などを用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金を支払わなければならない(第30条2項)。対象となるデジタル方式の特定機器と特定記録媒体は、現在、DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)、DCC(デジタル・コンパクトカセット)、MD(ミニ・ディスク)の3種類とそれらに対応した生テープ及び生ディスクと定められている。なお、録画については、一般向けの発売動向を踏まえて定められる予定である。補償金はこれらのデジタル機器及びテープなどの販売価格に含まれているので、メーカーは当該額を指定管理団体(社団法人私的録音補償金管理協会)に支払う義務を負う。
10-5-3 引用と表現
公表された著作物は、引用して利用することができる(第32条)が、著作物のデジタル化にともない他人の著作物を自分の著作物の中に取り込むことが容易になるので、「引用」にはじゅうぶん注意する必要がある。引用は、公正な慣行に合致し、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
最高裁昭和55年3月28日判決の「パロデイ=モンタージュ写真事件」において、最高裁は、他人の写真を無断で合成して作成したパロディ写真が、原作の正当な引用にはあたらず写真の一部を無断改変したものであり、また原作の著作者人格権の同一性保持権を侵害するものであるとした上で引用の範囲について初めて判示した。
この判決を踏まえて、正当な「引用」の一般的基準は次の5点とされている。
①他人の著作物を引用する必然性があること
②自分の著作物と引用部分とが明瞭に区別されて認識できること
③自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
④その引用が引用される著作者人格権を侵害するような態様でなされるものではないこと
⑤出所の明示がなされていること
わが国では、明治32年に著作権法(旧法)が制定され、近代的著作権制度が開始された。その後昭和45年の全面改正を経て、翌昭和46年から現行著作権法が施行された。近年、新たなデジタル技術の進展にともない、マルチメディア時代に適応すべく著作権制度の再構築が検討されはじめている。
10-6-1 デジタル技術の著作権への影響
著作権法は、複製権を中心として著作者が自分の著作物を利用する行為をコントロールすることによって経済的、人格的利益を保護することを基本とし、著作物が他人によって無断で利用された場合、著作者は自己の権利が侵害されたとして、差止めおよび損害賠償請求によって自分の権利を主張できることを前提としている制度である。
従来、著作物はさまざまな表現形式に分類され利用されてきた。しかし、デジタル技術は文字、音声、静止画、動画などすべての表現をデジタルデータ化することによって従来の表現形式を分解し、多様な情報を統合的に利用することを可能にした。また、デジタルデータは素材の個別情報として存在し、ネットワークなどによる送信が容易であるため、日本国内ばかりでなくインターネットなどを通じて全世界に送信され分散化されてしまう可能性もある。このような状態においては、デジタルデータとしての著作物は複製や改変などが容易であるばかりか、複製によっても品質が低下しないので、著作物に対する侵害発生の識別自体が困難になる。結果的には、従来の制度が原則としている著作者が著作物の利用をコントロールすることが不可能になり、それによって現行の著作権制度がうまく機能しなくなると考えられる。
10-6-2 今後の課題
現行著作権法は、新技術の開発・普及に対応して数度の部分改正を行ってきたが、現行著作権制度はアナログ技術を前提としたものであり、マルチメディア・ソフトの存在や多様な利用方法などを可能にするデジタル技術はまったく想定していない。また今後、デジタル技術が進展する過程で、従来のアナログ技術がなくなるわけではなく、同時に多様な著作物が存在することになり、制度上の問題は複雑さを増すばかりである。
著作権制度は著作者の利益を保護することが第一の目的である。また、著作権は私権であるから、自分の権利の行使については自らが決定できる権利である。いままで、著作者はある限られた存在のように思われてきた。しかし近い将来、デジタル技術とネットワーク環境の整備にともない、情報の自由な利用、自由な表現を前提とし、従来のメディアでは一方的に情報の受け取り手であるわれわれ個人がすべて著作者になる可能性のある社会が到来すると考えられている。このような社会環境においては、著作権の法的保護をあまり重要視すると情報が滞り、かえって弊害をもたらすことにもなりかねない。また一方、著作物に対する価値観が変容し著作者自身の権利保護についての考え方も多様化していくと思われる。したがって今後は、権利の保護と著作物の円滑な使用および公正な利用とのバランスをいかに図るかがますます重要な問題となる。これらの問題に対処していくには、そして、デジタル文化を確立するためにも、まず権利者のみならず利用者相互が著作権の内容を正しく認識することが望まれる。
【参考文献】
著作権テキスト平成7年度文化庁.
2)加戸時行:著作権法逐条講義改訂新版,社団法人著作権情報センター,(1994).
3)半田正夫:著作権法概説第七版,一粒社,(1994).
4)別冊ジュリスト「著作権判例百選(第二版)」有斐閣,(1994).
5)著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書,平成5年11月,文化庁.
6)著作権審議会マルチメディア'」倭員会第一次報告書-マルチメディア・ソフトの素材として利用される著作物に係る権手拠理を中心として-,平成5年11月,文化庁.
7)著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ検討経過報告一マルチメディアに係る制度上の問題についてー.平成7年2月,文化庁.