|
�@�ʓI�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʓI�@�@ �@�Ǝ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ėp���@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@��F�D�I �}�P�@�C���^�r���[�̖ړI�Ƃ�����̂̈ʑ� |
|
�ԑg�C���^�r���[�̗��_�ƕ��@ |
|
|
�P.�@�ԑg�C���^�r���[�̈Ӗ� 1.1�@�C���^�r���[�̖ړI�ƈʑ� 1.2�@�ԑg�C���^�r���[�̌��ʂƉۑ�@ 1.3�@�ԑg�C���^�r���[�̃R�~���j�P�[�V�������f�� 1.4�@�ԑg�C���^�r���[�̋���I�Ӌ` �Q.�ԑg�C���^�r���[�̍\�� 2.1�@�ԑg�̕��j�ƃC���^�r���[�̑O�� 2.2�@��ތ^�C���^�r���[�Ɨ\�蒲�a�^�C���^�r���[ 2.3�@�C���^�r���[�̈ʒu�Â��ƍ\�� 2.4�@�C���^�r���[�̕ҏW�Z�@ |
�R�D�ԑg�C���^�r���[�̕��@ 3.1�@�ԑg�C���^�r���[�̌`�� 3.2�@�@�ނ̑I���Ǝg�p���@ 3.3�@�C���^�r���[�̃X�^�b�t 3.4�@�C���^�r���[�̉f�� �S�D�ԑg�C���^�r���[�̓��e 4.1�@�C���^�r���[�̗v���Ƒg�ݗ��� 4.2�@�C���^�r���[�̎p�� 4.3�@�C���^�r���[�̌��t�ƓW�J 4.4�@�C���^�r���[�̗��ӓ_ �T.�Љ�I�Θb�Ƃ��Ă̔ԑg�C���^�r���[ |
�ԑg�C���^�r���[�ɂ́A���܂��܂Ȏ�ނ���@������A����𗝉������ʓI�Ɏ��{���邱�Ƃɂ���āA�ԑg�ɐl�ԓI�Ȗ��킢��[����^����L���ȕ\����@�ƂȂ�B�ԑg�C���^�r���[�́A���z�I�Ȏ����҂�z�肵�Ă����Ȃ���Љ�I�Θb�ł���A���̎��H�́A������Ƙb����̗�����킸�A���҂̐S�ւ̑z���͂���݁A����̎p�����Ɏʂ��Č��������ƂɂȂ���A�D�ꂽ�R�~���j�P�[�V�����\�͂̊w�K�̌��ł���Ƃ�����B�w���҂́A���̂悤�Ȕԑg�C���^�r���[�̈Ӌ`�Ƃ��̕��@�ɂ��Ă悭�������A�w�K�@��̑n�o�ɓw�͂��邱�Ƃ����߂���B
�P.�@�ԑg�C���^�r���[�̈Ӗ�
1.1�@�C���^�r���[�̖ړI�ƈʑ�
�C���^�r���[�ii
�C���^�r���[�́A�Љ����}�[�P�e�B���O�A��Â�J�E���Z�����O�A�w�K�w����g�D�̐l���A�����ĕ�m���t�B�N�V�����E���|���^�[�W���̂��߂̎�ފ����ȂǁA���܂��܂ȏ�ʂł����Ȃ���B�Ȋw�I�ȃC���^�r���[�͎��I�]�������̂��߂̗L�p�Ȏ�@�ł���A���̎��{�ɍۂ��ẮA���m�Ș_�����Ən���̎�@�����߂��m������Ă����B�܂��A�C���^�r���[�́A���v�I�E�}�X�I�Ȏ��_��������͌����Ƃ��ꂪ���Ȗ���������A�����҂̐S���N�w�ɐG��āA�������ꂽ��w�肷��M�d�ȋ@��ƂȂ邱�Ƃ�����B
�C���^�r���[���s���ҁi������j�ƁA�C���^�r���[����ҁi�b����j���ړI�Ƃ�����̂ɂ���āA�C���^�r���[���ǂ̂悤�Ȉʑ�����������}1�ōl���Ă݂邱�Ƃɂ���B
|
�@�ʓI�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʓI�@�@ �@�Ǝ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ėp���@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@��F�D�I �}�P�@�C���^�r���[�̖ړI�Ƃ�����̂̈ʑ� |
�����́A�C���^�r���[�̖ړI���A�b����̓����̂Ȃ��Ɍ����o�����Ƃ��Ă���̂��A�X�̘b����̃p�[�\�i���e�B�ɂ��ƂÂ��Ɠ��Ȃ��̂Ȃ̂��A�����ł͂Ȃ��āA�ق��̑����̐l�X�Ƃ����ʂ���ėp���̍������̂Ȃ̂����������̂Ƃ���B
�Ⴆ�A����|�p�Ƃ̂���܂ł̐l���ɂ��ĕ����ꍇ�́A���̉����ʓI�Ō��I�ł��邱�Ƃɏd�����u����邱�Ƃ��������낤���A���鏤�i�ɑ������҂̍D�������̗��R���ꍇ�́A�b����̌������A���̉̔ėp���ɏd�������邾�낤�B
�e���r�ԑg���X���ő����̒ʍs�l�ɃC���^�r���[������悤�ȏꍇ�A��ʂɉf��̂͌X�̐l�����A���̑����̔������ҏW�łȂ����ė����ƁA���ꂪ�S�̂Ƃ��Ắu���_�v�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ�ۂÂ����邱�Ƃ�����B
�����Ɉ�l�������ɓƓ��Ȉӌ����q�ׂ��l�����Ă��A���ꂪ�ҏW�ŃJ�b�g����Ă��܂��Ƃ���A����͂��̃C���^�r���[���A�ʐ������ėp���������o�����ƂɖړI�����������炾�ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B
�c���́A���̃C���^�r���[���A������Ƙb���肪�ړI�������āA�F�D�I�ɍs������̂Ȃ̂��A�ړI���������Ă���A�Ƃ��ɓG�ΓI�ɍs���邱�Ƃ�����̂��Ƃ������ł���B����n��̊ό��ē�����K�˂āA�y�n�̎j�Ղ▼���ɂ��ăC���^�r���[���邱�Ƃ́A�b����ɂƂ��Ă��悢��`�ɂȂ邩��A�������ɋ��͓I�Ȃ��̂ƂȂ�ł��낤�B
�����ۂ��ŁA�X�L�����_���ɒǂ��Ă��鐭���Ƃ�|�\�l�Ȃǂ̓C���^�r���[���瓦���悤�Ƃ�����A�����ȑΉ������Ȃ�������A�t�Ɏ����ٖ̕��ɗ��p���悤�Ƃ�����A�Ƃ��ɂ͋��U���܂������咣���s�Ȃ����Ƃ��邩������Ȃ��B
�����l����ƁA�C���^�r���[�Ƃ́A�u�F�D�I�v�ɂ����Ȃ��邱�Ƃ����邪�A���Ƃ��āu��F�D�I�v�ȊW�̂��Ƃɂ����Ȃ����ʂ������ď��Ȃ��͂Ȃ��̂ł���B
�����Ŗ��炩�ɂȂ邱�Ƃ́A�C���^�r���[�̂�����ɂ͂��܂��܂Ȉʑ�������A�]���Ă��̂��߂̕��@�͈ꌳ���ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�C���^�r���[�̖ړI�ɂ���āA�����̐l�ɓ������t�Ƙ_���Ŏ��₵���ق����ǂ��ꍇ�ƁA�l�̃p�[�\�i���e�B��T���āA�Ǝ����̍�����������Ă����ׂ��ꍇ������B�b����ɑ��čőP�̗�V��s�������Ƃ��ǂ��ꍇ���������A�A�|�C���g�����g�Ȃ��ʼn��������ċl�₵����A�킴�Ɩ���������U���������ŁA���̈�_��Njy���邱�Ƃ��A�����ĊԈ�������@�Ƃ͂����Ȃ����Ƃ�����B
���̂悤�Ȉʑ��́A���Ԃ̎��ԓI�o�߂◧��̈Ⴂ�A�Θb�̈Ӗ��@����͗ʂȂǂɂ���āA�����Εψڂ���悤�Ɍ�����B���Ƃ��A���t�����k�ɐ��ѕs�U�̗��R�������˂邱�Ƃ͋��t�ɂƂ��Ă͈�����Ƃ��Ȃ��F�D�I�C���^�r���[�ł��A���k�ɂƂ��Ă͎�
���Ă���悤�Ɋ�����G�ΓI�C���^�r���[�ł��邩������Ȃ��B�܂��A��q����悤�ɁA�����啪��ɏG�ł��l�ɁA���̋Ɉӂ��Ƃ������C���^�r���[�ł́A�����ʓI�Ȗ��ɔ���Ȃ���A���̐l���̐�������M�O�Ƃ��������̂��A�Ђ낭�Љ�̐l�X�̐S��ł悤�ȕ��Ր��������Ă��邱�Ƃ����邾�낤�B
�ǂ̂悤�ȃC���^�r���[���ǂ��C���^�r���[�����l����Ȃ�A���̕��@�̑I���Ƃ́A���̂悤�ȃC���^�r���[�̖ړI�̈ʑ��ƕψڂɂ��킹�Ȃ���œK����}��ق��ɂ͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B
1.2�@�ԑg�C���^�r���[�̌��ʂƉۑ�@
�@�{�_�ł́A�f���ԑg�̐���ɂ�����C���^�r���[�̕��@�ɂ��čl�@���邱�ƂƂ��A������u�ԑg�C���^�r���[�v�Ƃ�Ԃ��Ƃɂ���B
�ԑg�ɃC���^�r���[��p����̂ɂ́A���̂悤�ȈӖ���ړI������ƍl������B
�@�����҂ł���b���肪����Ă���Ƃ���������邱�Ƃɂ��A���̖�肪�{�����Ƃ����؋����������Ƃ��ł��A�ԑg�ɋq�ϐ���{���炵���A���͂┗�^�������������B�ԑg�̃��|�[�^�[���A�u����W�҂́A�������ƌ����Ă��܂����B�v�Ɠ`������A��ʂ̒��ɂ��̓��l���o�Ă��Ĕ������Ă���Ƃ����������ق����A�{���炵��������킯�ł���B
�A�����̓��e�����łȂ��A�\��̗l�q��̒��q�Ȃǂ��ӂ��߂��L���ȏ��A���Ȃ킿�b����̐l���⊴��A���̔w�i�ɂ�����Ȃǂ�`���邱�Ƃ��ł���B�b���莩�g�ł���A�����ł͌��ꉻ���ɂ������̕��G��������������`���邱�Ƃ�����B
���ꃁ�f�B�A�����ۓI�ŗ����I�Ȃ��̂�`��������������̂ɑ��āA�f�����f�B�A�͋�̓I�ŏ�I�Ȃ��̂�`����͂������B�ԑg�C���^�r���[�Ƃ́A�����Ō���錾�t�̓��e�ƁA��������\������܂��āA���Ȃ킿���ꃁ�f�B�A�Ɖf�����f�B�A�̗����̓������������āA�����҂̔F�������[�߁A�ԑg�ɐl�ԓI�ȓ��Â��≜�s�����������邽�߂ɗp������̂��ƌ����悤�B
�ԑg�C���^�r���[�́A���̂悤�Ɍ��ʓI�Ȃ��̂����A����䂦�ɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B
��1�ɁA�C���^�r���[�ɂ͖c��ȏ�܂܂�Ă���̂ŁA�����œ`�����邱�Ƃ̉����Ӗ��̂���d�v�ȏ��Ȃ̂������Ȃ���A�ԑg�̃��b�Z�[�W�͍������A�����҂ɂ��`���ɂ������̂ƂȂ�B�C���^�r���[�ʼn����ǂ̂悤�ɓI�m�ɕ��������̂��A�ԑg�̍\���i�ҏW�j�ɂ����āA�����Ɏ�̑I�����邩�͑傫�ȉۑ�ƂȂ�B
��2�ɁA����䂦�Ɋ��������ԑg�̂Ȃ��œ����ҁi�b����j���ʂ�A�������Ă��Ă��A���̎p�͔ԑg�̍���̈Ӑ}�ɂ���č\�����ꂽ���̂��Ƃ������Ƃł���B�����҂ɂƂ��ẮA�ԑg��ʂ��ĎƂ߂��Ώہi�b����j�̈�ۂŁA���̐l���ւ̕]��������Â����Ă��܂��i�ꕔ�������đS�̂��Ǝv���Ă��܂��j���Ƃ�����B���肪�Ӑ}����ɂ���A���ӎ��ɂ���A�C���^�r���[�̌�����p������������l���ς��`�����A�Љ�I��������E���Ă��܂����Ƃ����蓾��B�����̐l�̃C���^�r���[��ԑg�̓��e�ɂ��킹�Ď�̂��邱�ƂŁA���̏��݂��������邱�Ƃ��ł���Ɠ����ɁA�l�X�̔����ӓI�ɑ��삵�Ă���\��������B
���̂悤�ɑ�1�Ƒ�2�̉ۑ�̊Ԃɂ́A��������v�f������B�C���^�r���[�ɂ���āA�����肪���߂���̂������o���Ƃ������Ƃ́A�b����̔�����U�����Ă���̂�������Ȃ����A�ҏW�ɂ���ăC���^�r���[����̑I�����邱�ƂŁA��ۂ⌋�_���䂪�߂Ă��邩������Ȃ��B
�ߔN�A�����̕���ł́A�u�T�E���h�o�C�g�v�Ƃ������t���g����悤�ɂȂ����B����́A�b����̔����̈ꕔ������āA�ԑg�̂Ȃ��ɂ����Z���A�f�ГI�ɗp���邱�ƂŁA�����ۂ���������ԑg�\���i�ҏW�j�̎�@�ł��邪�A���̓K�ۂɂ��Ă͂����c�_�̓I�ƂȂ�Ƃ���ł���B
�]���ăC���^�r���[�̑�3�̉ۑ�́A�ԑg�C���^�r���[�ɂ�����q�ϐ�����������ǂ̂悤�Ɋm�ۂ��Ă������Ƃ������Ƃł���B���̓_�ɂ����āA�ԑg�̍���ɂ́A�����ւ̕����̐��_�̂��ƂɁA��Ɏ��o�I�Ȗ��ӎ��������ď��̎�̂�ԑg�̍\���������Ȃ����Ƃ����߂��Ă���̂ł���B
��ʂɁA�����҂̓C���^�r���[�̕�����̗���Ɏ���̋C�������������Ĕԑg���������悤�Ƃ��邵�A�܂��A���̂悤�Ȋ��o������₷���悤�ɔԑg���\������Ă��邱�Ƃ������B���̏ꍇ�A�b����̎咣������I�ɕ������������A�����肩��Ƃ��ǂ�������Ȃ������āA����ɓ����Ă��炤�X�^�C�����Ƃ邱�ƂŁA�����҂͎����̗͂ł��̃R�����g�������o�����Ƃ��ł����悤�Ɋ�������A�����œW�J����Ă���咣��v�z���A�����������炪�������������̂ł��邩�̂悤�ɍ��o���邱�Ƃ�����B�������Ď����҂́A�ԑg�̓��e���q�ϓI�Ō����Ȃ��̂��ƎƂ߂Ă��܂������Ȃ̂ł���B����͔ԑg�C���^�r���[�̑傫�Ȍ��p�ł���A�C���^�r���[�Ƃ����X�^�C���́A�ԑg���q�ϐ����������Z�������Ƃ��ɍD��ŗp�������@�Ƃ�������B���̂��Ƃ́A�ԑg�̍���⎋���҂��A���イ�Ԃ�ɒ��ӂ��Ă����ׂ��_���Ƃ����悤�B
�Ⴆ�A���鏤�i��̔����悤�Ƃ��Ă���ԑg�ŁA�����肪���i�ɂ��Đu�ˁA�b����͂��̒������������A������肪���S���ĕ�����������A���Q�̐��������ē��ӂ���Ƃ������W�J�ɂ���āA�����҂̍w���ӗ~���h������悤�Ȕԑg�̏ꍇ�A����̓C���^�r���[�Ƃ����X�^�C���������o���A�����̋q�ϓI�ȕ��͋C�̂悤�Ȃ��̂�Z��������I�Ȑ�`�ł���ƌ�����B�C���^�r���[�̈ʑ��ł����A������Ƙb����̖ړI�����S�Ɉ�v�����A����Ήߏ�ɗF�D�I�ȃC���^�r���[�Ƃ������̂́A���͑Θb�ł͂Ȃ��A�����咣�������ōs�Ȃ��Ă���킯�ł���B���̈Ӗ��ł́A�C���^�r���[�̕�����Ƙb����Ƃ̊Ԃɂ́A�F�D�I�ȂȂ��ɂ��K�x�ȋْ������Ƃ��Ȃ��āA���݂��ɑΘb�̓��e�������ŋq�ϓI�Ȃ��̂Ƃ���w�͂��͂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł���B
1.3�ԑg�C���^�r���[�̃R�~���j�P�[�V�������f��
�����ŁA�ԑg�C���^�r���[�i�ԑg����̂��߂̃C���^�r���[�j���A���̂ق��́i�ԑg����O��Ƃ��Ȃ��j�C���^�r���[�Ƒ��Ⴕ�Ă�����F�ɂ��čl���Ă݂�B����́A�ԑg�C���^�r���[�ł͑����̏ꍇ�A������ii
�ԑg�C���^�r���[�ł́A�����̏ꍇ�A�b����́A�����肩��̎���ɓ�����̂Ɠ����ɁA�����҂��ӎ����Ȃ���b�������邱�ƂɂȂ�B��������܂��A�b����ɑ��A�����҂̋�������悤�ȁA���邢�͎����҂��\����悤�Ȏ�������悤�Ƃ���B�������āA������Ƙb����́A�����ʓI�Ȏ����ґ���z�肵�A���̔�����m�����x���Ƃ��������̂��������Ȃ���A���������l�X�ɗ������Ă��炦��悤�ȑΘb���s�����Ƃ���̂ł���B
�Ⴆ�A���镪��̐��ƂɃC���^�r���[������ꍇ�A�ЂƂ̐��I�Ȍ��t�ɂ��āA�����莩�g�����O�ɂ悭�������Ă��āA���͂╷���K�v�̂Ȃ����Ƃł��A���炽�߂Đu�˂Ă݂邾�낤���A�b����͂�����Ղ���������������A�K�X����������Ȃ���A�b���������߂邱�Ƃł��낤�B�܂��ʂ̃C���^�r���[�ł́A�l�I�Ȗ{�������̂܂ܓf�I���邱�Ƃɍ�����肪����A���t��ۂݍ���A�\����ς����肷�邱�Ƃ����邾�낤�B���̂悤�Ȕz���͒��O��O�ɂ������_�̏�Ȃǂł����l���낤���A�ԑg�C���^�r���[�̏ꍇ�́A��ʎ����҂͖ڂ̑O�ɂ��炸�A���̏�ł̔������Ԃ��Ă��邱�Ƃ̂Ȃ����z�I�ȑ��݂ł��邱�Ƃ������ł���B
�������́A�����̎����҂Ƃ������Ԃ��Ƃ��Ȃ��Ă͂���̂����A�����ɓ���̒N���Ƃ������Ƃł��Ȃ��A����ΎЉ�I�ɋ��L�\�ȉ��z�I���݂Ƃ����ׂ����̂ł���B�ԑg�C���^�r���[�̘b����ƕ�����́A�����̓�l�̐l�ԊW���痣��āA���̂悤�ȉ��z�̈�ʓI�����҂����Ȃ��Ă���ł��낤�펯��ǎ��ɏƂ炵�Ȃ���A���������̘b���̓��e�A���t�����A����̕\�o�A���Ƃ̑ł����Ȃǂ�I�����A�g�ݗ��ĂȂ���b�������Ă���̂��Ƃ�����B
���̂悤�ȁA����ΐl�H�I�ȑΘb�������Ȃ����Ƃ́A������Ƙb����ɂ����ْ̋��╉�S����������A�����̂��Ƃ��悭�����悤�Ƃ��āA�I�[�o�[�Ɍ����Ă݂��苕�U���܂������肷�錴���ƂȂ邩������Ȃ����Ƃɂ͒��ӂ��K�v�ł��낤�B
���������̈���ŁA�ԑg�C���^�r���[�ɂ͑Θb�̓��e����蕁�ՓI�Ő������ꂽ�����̂��̂ւƍ��߂Ă�����p�����邱�Ƃ��A�w�E�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�b����́A�C���^�r���[����Ƃ������ƂŁA���݂�F�߂�ꂽ��т���������A����܂ł̎����̎��тɎЉ�I�ȈӋ`�������o�����Ƃ��ł�����A�������g�����R�ƕ����Ă������ӎ��ɂ��āA������̌��t�ɐG������ĔF����[�߂���A���ꉻ�ł���Ƃ������Ƃ����邾�낤�B���̂��ƂŐl�ԓI�Ȑ����⎖�Ƃ̔��W���������\���������邾�낤�B�����āA���̂悤�ȃP�[�X�́A�����I�݂ȕ����肩�甭����U���邱�Ƃɂ���āA�����炳��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��悤�Ɏv����B
���镪��⓹���ɂ߂��l�ǂ����̑Βk�́A�����̎����҂��䂫���邵�A������Ƙb����Ƃ̊Ԃ̎��������ݍ����āA�L���Ȋ����������b�����e�ރC���^�r���[�����邱�Ƃ́A�S�y�������̂ł���B�D�ꂽ�ԑg�C���^�r���[���ӏ܂���ƁA���Ƃ��l�I�Ȃ��Ƃ�����������C���^�r���[�ł��A�����҂͂����ɕ��ՓI�ȓN�w����_�������o���A��������l�����Ƃ��������̂��w��ł��邱�Ƃ�����̂ł���B
���̏ꍇ�A�����҂��A�ԑg��ʂ��Č����o�����Ƃ��Ă���̂́A���͕�����Ƙb����̑Θb�����ĕ����яオ���Ă��邠���̎Љ�I���L�T�O���Ƃ������Ƃ��ł���B����̓C���^�r���[�̕�����Ƙb���肪�z�肷�鉼�z�I�����҂̎p�ɂ��قڏd�Ȃ���̂̂悤�Ɏv����B���̂悤�ȎЉ�I���L�T�O���A�����ł̓O�����h�E�X�g�[���[�iground story�j�ƌĂԂ��ƂƂ��āA�����}�Q�̃R�~���j�P�[�V�������f���ɏd�˂��̂��}�R�ł���B
���̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�������f�����A�����̎����҂̑����猩��ƁA������Ƙb����̑Θb���K���X���̂悤�ɓ��������āA�����ɔ��˂��鎩���̎p�Ƃ����Ԃ点�Ȃ���A���̃O�����h�E�X�g�[���[�������o���A�������炳�܂��܂Ȉ�v�_�⑊��_�����Ȃ���A�����ۂ�������芴�����Ƃ��Ă���̂��Ǝv����B�������A���̂悤�ȎЉ�I�O�����h�E�X�g�[���[�́A����n��A����╶���ɂ���đ��Ή��������̂ŁA��������邪�A��ʂł͖����⎞��������Ր�������Ă�����B�ԑg�C���^�r���[�̗�Ɍ��炸�A�h�L�������^���[��h���}�A�����Ă��܂��܂ȕ\���s�ׂɂ����āA���̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�������f���́A���藧������̂ł͂Ȃ����ƍl������̂ł���B
|
������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b����@�@ i �@�@�@�@�@�@ �@�@ ������ �@ �@�@�@�@�@ �@ audience �@�@�@�@�@�@�@ �}�Q�@�ԑg�C���^�r���[�̃R�~���j�P�[�V�������f���P |
|
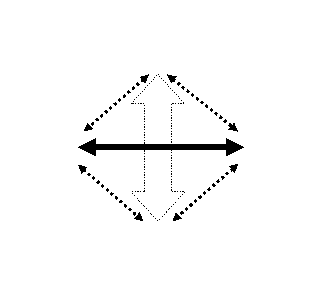
|
�Љ�I���L�T�O �@ �@�@�@�@�@ ground
story ������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b����@�@ i �@�@�@�@ �@�@�@�@ ������ �@�@�@�@ �@�@�@ Audience �}�R�@�ԑg�C���^�r���[�̃R�~���j�P�[�V�������f���Q |
|
1.4�ԑg�C���^�r���[�̋���I�Ӌ`
�ԑg����ɂ́A�A�}�`���A����v���܂ŁA����`�Ԃ���J�͈̔͂Ȃǂ��܂��܂ȑԗl�����邪�A����ł��āA�ǂ̔ԑg�ɂ����Ă��A�����ɑz�肳��鉼�z�I�Ȏ����҂̂�����ɂ́A����قǑ傫�ȍ��ق�����킯�ł͂Ȃ��Ǝv����B�v���ɂ����̂ł��A���Z�����w���̎�ɂ����̂ł��A�ԑg�𐧍삷�邱�Ƃ͎Љ�Q���̍s�ׂł���A���̓��e�͂Ђ낭�Љ�I�ǎ�������̕����̐��_�ɍ��v�������̂łȂ���Ύ�����Ȃ��͂��ł���B
�ԑg�C���^�r���[���s�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A������Ƙb����̑o�����A���ꂼ�ꑊ��̑��݂�F�߁A����̗����v���ɑz���͂����A�����ɌX�̗��������荂���ȎЉ�I���L�T�O�i�����܂ŏq�ׂĂ����O�����h�X�g�[���[�j���ӎ����āA����ɏ]���������������Ȃ����Ƃ��邱�Ƃł���B
���Ȃ킿�A�ԑg�C���^�r���[�Ƃ́A�u�Љ���Ƃ��Ȃ����Θb�v�Ȃ̂ł���A���̗͂��琬���Ă������Ƃ́A��{�I�ȃR�~���j�P�[�V�����\�́A�Ђ��Ă͑����I�Ȑl�ԗ͂̈琬�ɂ����Ă��傫�ȈӋ`�����邱�Ƃ��낤�B
����̎�҂ɂƂ��ẮA�Љ�I�펯��ǎ����ӎ����Ȃ���A�Ă��˂��Ȍ��t������ԓx�őΘb������Ƃ����i�����Ȃ��j�M�d�ȌP���̏�Ƃ������ƂɂȂ�B�J������}�C�N�͂��̂悤�ȋ@���^���Ă���镑�䑕�u�Ƃ����킯�ł���B
���k�ǂ�����A���t���܂����ẴC���^�r���[�����K���Ă݂邱�Ƃ͑傫�ȈӖ�������B���̍ہA�K���A������E�b����E�J�����}���Ȃǂ̖�������サ�ĉ����邱�Ɓi���[���E�v���C���O�j����ł���B�C���^�r���[�̎�����ď��ɓ����邱�Ƃ́A�����ĈՂ������Ƃł͂Ȃ����A�C���^�r���[���邱�Ƃ́A�����Ȍo���ł͂Ȃ����Ƃ���������B
�l�Ԃ́A�J������}�C�N����������ƁA�̂͌����Ȃ�A�O�������B���������ꂵ�����Ƃ��Ȃ����̂��Ƃ������Ƃ�m���Ă������Ƃ��A�ԑg�̍���ɂƂ��Ă͕s���ȑf�{�ł���B���ꂪ�Ȃ��҂́A���l�ɃJ������}�C�N���ނ��邱�Ƃɓ݊��ƂȂ�A���̍s�ׂ��Ƃ��ɈЈ��I������������Ȃ��̂Ƃ��Č����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ͂��Ȃ�����ł���B�����č���̑����u�B���Ă���Ă���v�ȂǂƂ����ӎ���������Ƃ͌��ł���B
�ԑg����̂��̂悤�ȑ��ʂɂ��Ē��ӂ��͂���Ă����Ƃ������Ƃ́A���f�B�A�̛s�ޖ��ɂ��Ă̂��[�����@�͂���ނ��Ƃɖ𗧂��낤�B
���Ƃ��A�w�Z����ɂ����āA����̎咣�𐮑R�ƁA�_���I�ɁA���X�Əq�ׂ�\�͂���ނ��Ƃ͔��ɏd�v�ł���B���̂悤�ȕ٘_��Θb�A���邢�͕��͂⎍�̘N�ǁA�����Ȃǂ̕��L���R�~���j�P�[�V�����\�͂̈琬�̈�̂Ȃ��ŁA�J������}�C�N���g�����\���\�͂Ƃ��Ă̔ԑg���싳��A�Ђ��Ă̓��f�B�A�E���e���V�[�Ƃ������̂��ʒu�Â�����Ƃ������ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�ԑg�C���^�r���[�Ƃ́A���̂Ȃ��ł��ł���{�I�ȉߒ��Ƃ��āA�傢�ɊS���Ă悢�e�[�}�ł���A�w�Z����̏�ʂł��A���v��I�ɂƂ肢����A���H����Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�Q.�@�ԑg�C���^�r���[�̍\��
2.1�@�ԑg�̕��j�ƃC���^�r���[�̑O��
�ԑg�C���^�r���[���s�Ȃ��ꍇ�̑O��ƂȂ邱�Ƃ���Ƃ��āA���̔ԑg�̂Ƃ�X�^���X����j�ɂ��āA�l���Ă����ׂ����Ƃ�����Ǝv����B
��1�ɁA�ԑg����̘g�g�݂�ړI�m�Ȃ��̂Ƃ��A����Ǝ�ޑΏہi���邢�̓C���^�r���[�̕�����Ƙb����j�Ƃ̊W���𐳂����\�z���Ă������Ƃł���B
�@�ւ�W���[�i���X�g���A�����҂̒m�錠����Љ�I���`�̒Nj��A�����̕����Ȃǂ̂��߂ɐ��삵�A�Љ�̂��܂��܂Ȗ��Â��}�X���f�B�A�ɂ���ē`���悤�Ƃ���ꍇ������A���鏤�i��T�[�r�X���`���邽�߂̔ԑg�����邵�A���Z�����w�����w�K�����̈�Ƃ��Đ��삵�A�Z�������ŗ�����邱�Ƃ�����B
���̌����������āA�ǂ̂悤�ȗ��ꂩ�瑊��ɃJ������}�C�N�������邱�Ƃ��������̂��A���̑O��⌋�ʂɍ���͂ǂ̂悤�ȐӔC�����Ƃ��ł���̂��ɂ���āA�ԑg�̐����C���^�r���[�̂�������A�قȂ������̂ƂȂ낤�B
�Ⴆ�C���^�r���[�̍Œ��ɁA�b���肪���ɂ܂��ċ����o������A���V�����肵���Ƃ���B���̎p���B���Ă��Ă��悢�̂��A���̏�ʂ����\���ėǂ��̂��́A���̂Ƃ��̏�ԑg�̖ړI�A����Ǝ�ޑΏۂƂ̊W���A����̐ӔC�̏��݂Ȃǂ̑O��̂��ƂœK�ۂ���܂�ł��낤�B
����Ǝ�ޑΏۂƂ̊Ԃɐ[���M���W������A�܂�{������������ƂȂ��L�^���邱�Ƃ͔ԑg�̓��e��[�߂邱�ƂɂȂ낤���i�܂��A���̂悤�Ȋ���\�o�ł���悤�Ȑl�ԊW�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��낤���j�A���̂悤�ȑO���W�����Ȃ��i�K�ł́A��݂����ɃJ������}�C�N�������邱�Ƃ�������Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ��A����Ƃ��Ă킫�܂��Ă����ׂ��ł���B
��ʘ_�ł����A�ԑg�̍���́A��ޑΏۂɑ��邶�イ�Ԃ�Ȓ��������A�����Ɨ����̂��ƂŁA�M���W���[���ނ���Ă���قǁA���e�̂���A�j�S�ɔ������C���^�r���[�͂��₷���ł��낤�B�C���^�r���[�̋����Ɩ��Ƃ����i�A�|�C���g�����g�j�Ƃ��납���߂ɂ��Ȃ����ԓx�Őڂ��A�ԑg�̖ړI�𗝉����Ă��炢�A�F�D�I�ɋ��͂��Ă��炦��悤�ɂ��邱�Ƃ́A�C���^�r���[�̂����Ƃ���{�I�ȑԓx�ƂȂ낤�B���̈Ӗ��ł̔ԑg����́A�J������}�C�N���������ނ����ƑO����X�^�[�g���Ă��邱�ƂɂȂ�B�l�ԊW�̍\�z�́A�K���������₷���l���Ă悢���̂ł͂Ȃ����A�ԑg����Ƃ����s�ׂ≿�l�ς��N�������������Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ́A�������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
��Q�ɁA�ԑg�́u���_�v�͂ǂ��ɂ���̂��A���̓��e�͒N�ɂ���Č���Ă���̂����l���Ă����ׂ����Ƃł���B��ʂɃC���^�r���A�[���o�ꂵ�A���̎�ނ����Ă����p��ǂ��Ă����A���̎v�l�⊴��̗���ɉ����Ĕԑg���W�J���Ă����ꍇ������A�C���^�r���A�[�͓o�ꂹ���A��ʂɂ̓}�C�N�̐悪�ʂ���x�ŁA�������̕�����ƂȂ��Ă���ꍇ������B
�����肪���n�̃C���^�r���[�̏�ʂ݂̂ɓo�ꂷ��̂��A�i���[�V���������˂�̂��A���̃i���[�V�����ɁA�u�������́v�u�����́v�Ƃ���������p����̂��A�Ȃǂɂ���Ă��ԑg�̎��_�̏��݂��ǂ��ɂ���̂��͈قȂ������̂ƂȂ낤�B
�ԑg�̍��莩�g���A�ԑg�𐧍삵�Ă��钆�ŋ^�����������A�����ɋ�������A�Y�肷��悤�ȍ\���ɂ���āA����ɍ���̑��݂Ǝ����҂̎��_������ɂȂ�A�����҂̊���ړ���U�����݂Ȃ���W�J���Ă����ԑg������A��ޑΏۂ���������҂̊���������āA��O�ғI�Ȏ��_����`���Ă���悤�Ɋ���������ԑg�����邾�낤�B�ǂ���̎��_�ɂ��Ӗ��͂��邪�A���̂悤�Ȏ��_����܂��Ă��Ȃ��ԑg���ƁA�X�g�[���[�̐c���ʂ��Ă��Ȃ��A�킩��ɂ�����ۂ��c�����Ƃ�����B�C���^�r���[�́A���̂悤�Ȕԑg�̎��_�̏��݂ɂ���Ă��A��������ς���Ă���ł��낤�B
�����ő�R�ɁA���̂悤�ȍ���Ǝ�ޑΏۂ̊W�����A�ǂ��܂Ŏ����҂ɂ������Ė������̂��Ƃ����u�W���̊J���v�Ƃ�������ɂ��Ă��l���Ă����K�v�����邾�낤�B�C���^�r���A�[�����łȂ��A�J�����}���Ȃǂ̃X�^�b�t���܂߂ĉ�ʂ̒��Ɏʂ��Ă��Ă��悢���Ƃɂ��āA�ł��������މߒ��Ȃǂ���ʂ̒��Ō����Ă����ȂǁA���̔ԑg�ɂ����������ޑΏۂƂ̊W�������҂ɂ��I�[�v���Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ��A�u�W���̊J���v�Ƃ������Ƃ�����B
���̂悤�ȊW�����B���āA����̉�݂��ɗ͊��������Ȃ��悤�ɍ��ԑg�����邵�A���̒��ԓI�ȏꍇ�����낤���A���̂悤�Ȕԑg�̕��j�ɂ���Ă��A�C���^�r���[�̂�����͈قȂ������̂ƂȂ��Ă��邾�낤�B
�������A���Ƃ�����̎p����ʂ̂Ȃ��Ɏʂ��Ă��Ă��A���Ȃ��Ă��A�����҂́A�ԑg�S�̂�ʂ��āA����̎p�������Ƃ�Ȃ���ԑg���������Ă��邵�A�����ɂ͉B���悤�̂Ȃ�����̐l�Ԑ��⋳�{�Ȃǂ����ݏo����̂ł���B����́A���̈Ӗ��ɂ����Ď���̎p����Ɏ����ҁi�����̎����҂ł�����A���z�I�����҂ł�����j����ώ@����鑶�݂Ƃ��āA���̐l�Ԑ������߂Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�ԑg�����\����Ƃ������Ƃ́A�Љ�I�ӔC���Ƃ������Ƃł���A����Ǝ����҂Ƃ̊W���̖��ɂ��ւ��Ƃ���ƂȂ�B�Ⴆ�Δԑg�C���^�r���[�̂Ȃ��ɂ́A���܂��܂Ȏ����A�b����̊���B�����萺��ς����肵�āA�N�̔��������킩��Ȃ����Ă���Ƃ�������B���̂悤�ȕ\������������̂ɂ́i�����҂����̔�����M����̂ɂ́j�A�ԑg�̍���ɑ���Љ�I�F�m��M�����s���ł���B���̊W���͐�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�����҂͔ԑg�̍���̎p���ɑ��āA��ɊĎ�����ԓx������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���B
2.2�@��ތ^�C���^�r���[�Ɨ\�蒲�a�^�C���^�r���[
�ԑg����̂��߂̃C���^�r���[�́A�u��ތ^�Ȃ�������^�C���^�r���[�v�Ƃ��������̂ƁA�u�\�蒲�a�^�C���^�r���[�v�Ƃ��������̂ɑ�ʂł���悤�Ɏv����B
�@��ތ^�i����^�j�C���^�r���[�@
�C���^�r���[���̂��̂���ލs�ׂł���A�C���^�r���A�[���X�^�b�t���i������x�A���O�̎�ދ��Ă���Ƃ��Ă��j���̌���ɏ��߂ē���A���̏�ŏ��߂Ęb�����Ƃ������̂ł���B
�A�\�蒲�a�^�C���^�r���[
���炩���߂̒�����ō����ł킩���Ă��邱�Ƃ��A���炽�߂Ęb���肩�����Ă��������A���O�Ɏ�ނ������e���J�����̑O�ōČ����Ă݂���悤�ȏꍇ�ł���B
���ۂ̔ԑg�ł́A������x�̂��Ƃ����O�ɒ��ׂĂ����Ă���A�X�^�W�I�⌻�n�œ��ӑ����ȃC���^�r���[���s�Ȃ��Ƃ����悤�ȁA��ތ^�Ɨ\�蒲�a�^�̒��ԓI�Ȃ��̂ƂȂ邱�Ƃ��������A������Ƙb���肪�A���������̑Θb���ԑg�Ƃ��Č��\����邱�Ƃ�O��ɁA���z�I�Ȏ����҂ւ��������s�Ȃ��Ă���ӎ��������ꍇ�ɂ́A����͂قƂ�Ǘ\�����a�I�ȍs�ׂƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B���Ƃ��A�ԑg�C���^�r���[�́A��ނ���鑤�̂���Ȃ�̏����⋦�͂Ȃ��ɂ͐������ɂ������̂ł�����B
�\�����a�^�̃C���^�r���[�ł����Ă��A����́A�ԑg�̂Ȃ��ł̐V�N�Ȕ�������������邩�̂悤�ɑ����邱�Ƃ������B������́A�����҂̎��_�ɗ����Ƃ��A���̗����������A����ړ������₷�����̂ƍl���āA���������O�ɒm���Ă��邱�Ƃł��A���炽�߂Ęb����ɕ������ƂɂȂ邵�A���̓����ɑ��āA���߂ĕ��������̂ł��邩�̂悤�ɁA�������芴�S�����肷��i���Ȃ킿�A���Z������j���Ƃ������B
�����������`���Ƃł������ׂ����̂����A���̂悤�Ȑ�����@�́A�悭���������A����̔ԑg����̂�����Ƃ��āA�Ђ낭��������Ă���X�^�C���ƂȂ��Ă���B
�t�ɂ����Ύ����҂́A�u�C���^�r���A�[�́A���߂ĕ������悤�Ȋ�����Ă��邪�A���Ԃ炩���ߒm���Ă����ɈႢ�Ȃ��v�ƁA��������������ԓx�Ō��Ă��邱�Ƃ��������낤�B
���f�B�A�����Ƃ��ẮA�{���Ȃ�A��ތ^�����������Ȃ��̂��낤���A�������┗�^�������邱�Ƃ��낤�B��ׂė\�蒲�a�^�̔ԑg�ł́A�ꍇ�ɂ���Ă͑�{��_�ǂ݂���悤�Ȃ������Ȃ��△�p�ȋْ����������A�ԑg�����Â炢���̂ɂ����˂Ȃ��B
���������ۂ̔ԑg����̂��߂̏�����i�s�̖ʂ�����A�ԑg���킩��₷�����邽�߂ɂ��A�v���E�A�}�`���A���킸�A���̗\�蒲�a�^�Ƃ������̂𑽗p������Ȃ����Ƃ̂ق��������B
���̏ꍇ�̏o���҂ɂ́A�������ꂽ��{���A�����������߂Ẳ�b�ł��邩�̂悤�Ɏ��R�ɒ�������A����L���ɕ\�����邱�Ƃ����߂���B����ɂ͂����̃^�����g�i�˔\�j���K�v�ȂƂ�������邪�A�P���ɂ���ďK�n������̂ł�����B
�\�蒲�a�^�̑�\�I�Ȍ`���Ƃ��āA�u�g�[�L���O�w�b�h�v�ƌĂ����̂�����B���O�̖Ȗ��Ȓ����ɂ���Ă��炩���ߊ������ꂽ�V�i���I������A���̓��e�ɉ����ē����҂��،������̃J�b�g���Ȃ����Ă������ƂŁA�ԑg���\������Ă����悤�ȃX�^�C���ł���B�C�M���X��BBC�����̔ԑg�Ȃǂɑ���������̂ŁABBC�����Ƃ����邱�Ƃ�����B���Ɏ茘���\���@�ł���A�_���I�ȓW�J�̔ԑg���ł������邪�A�_���̊G�����ɂ����Ȃ��悤�Ȗ��C�Ȃ��������邱�Ƃ�����B
�܂��A�����肪�قƂ�ǎ���������邱�ƂȂ��A�b���肪����̒m����l���X�Ƙb��������u�b�`���Ƃł������ׂ��X�^�C���̃C���^�r���[�����邪�A���̂悤�ȏꍇ�̓C���^�r���[�Ƃ������͍u���≉���ɋ߂����̂Ƃ����邾�낤�B
2.3�@�C���^�r���[�̈ʒu�Â��ƍ\��
�ԑg�S�̂̃o�����X�̒��ŁA�C���^�r���[���ǂ̂悤�Ɉʒu�Â��邩�ɂ���Ă��A�K�v�Ƃ����C���^�r���[�̂��������@�͈قȂ��Ă���B�ԑg�̂ǂ��ɂǂ̂��炢�̕��ʁi���Ԃ̒����j�A�ǂ̂悤�ȏd�݂Â��ŃC���^�r���[��p���邩�i�ǂ̒��x�̏d�݂̂���ŃC���^�r���[������̂��j�A�Ƃ������ł���B
��l�̘b����ɂ��ẴC���^�r���[�𒆐S�Ƃ��č\������A���̂ق��̉f���́A�b����̌��t��⊮����悤�Ȗ����Ŏg����悤�ȁA�C���^�r���[���̂��̂ɑ傫�ȏd�݂�����ԑg������A����C�x���g���̏o���ŁA�ޏꂵ�Ă���l�X���炲���Z�����z��Α����Ƃ����悤�ȏꍇ������A����ɂ���ăC���^�r���[�̑O�����@���قȂ������̂ɂȂ邾�낤�B
�������ꂽ�ԑg�̒��ŁA��l�̘b����ɂ�������C���^�r���[���A�������Ăĕ����Ă������Ƃ��A�C���^�r���[�̒���I�ȍ\���Ƃ���Ȃ�A�ҏW�ɂ���ĕ����̐l�X�̃C���^�r���[�������Ɍ����Ă������Ƃ͕���I�ȍ\���Ƃ����邾�낤�B����ɕ����̔��������݂ɑg�ݍ��킹�āA������т����点��悤�ȏd�w�I�ȍ\���Ƃ����ׂ����@������Ǝv����B
�\1�@�C���^�r���[���d�w�I�ȍ\���̗�
�@�@�@�i�w����X�e�[�V�����x2004�N�x��X��u����!�X�̃R���T�[�g�`��t�����N�����I�[�P�X�g���v�̈ꕔ�j
|
�� |
�f�@�@�� |
���@�@�@�e |
|
��1 |
|
�i���[�V�����@�u�I�[�P�X�g���̒��j��S���Ă��鍂�Z���̒c�������ɁA���b�����Ă݂܂����B�v �f�B���N�^�[�@�u�I�[�P�X�g������������Ă��āA�ǂ��������ƁA�y�������Ƃ́A�ǂ�Ȃ��Ƃł����H�v |
|
��2 |
|
A����@�u���y���Ԃ��������������ƂƁA���E�I�ɂ��L���Ȏw���҂̕��ɂ��U���Ă��炦�ĂƂĂ��K���ł��B�v |
|
��3 |
|
B����@�u���y�̋Z�p�ʂ��A�l�ԓI�ɂ��A�{���ɂ��낢�닳���Ă�����ŁA�c���ł��邱�Ƃ��ւ�Ɏv���Ă��܂��B�v |
|
��4 |
|
C����@�u�����ȔN�̐l�Ɗւ�肪���ĂāA���ʂ̊w�������ł͊ւ��̂��ĂȂ��悤�ȔN�̐l�ƁA�ւ�肪���Ă邱�Ƃ��ǂ��������Ƃ��Ǝv���܂��B�v |
|
��5 |
|
A����@�u�����搶�́A���y�ɂ��l�Ԃ̓��ʓI�Ȃ��Ƃɂ��A�ƂĂ��������̂ő�ςł��B�v |
|
��6 |
|
���K�ꕗ�i�i���n���͂Ȃ��E�����搶�̐��݂̂��d�Ȃ�j �����搶�i���̂݁j�@�u��ԑ厖�Ȃ��Ƃ́A��͂�l�ԓI�ɗ��h�ɐ������Ă����Ƃ������Ƃł�����A�S�̋���Ƃ����t�����Ƃ����낢��ƁA�����ĎЉ�ɏo�čs�����Ƃ��ɗ��h�Ȑl�ԂƂ��Ă���Ă�����悤�Ȃ��Ƃ��A��ԍl���Ă���Ă��邵�A�v |
|
��7 |
|
�����搶�@�u�W�c�����̒��ł��낢��Ȃ��Ƃ��w��ł����A�����o�����Ă������Ƃ́A��͂�Љ�ɏo�đ�l�̎Љ�ɓ����Ă��A�݂�Ȃŋ��͂������ċ����������Ă����Љ������Ă����A�����������̂̏k�}���Ǝv���܂��̂ŁA�I�[�P�X�g����ʂ��Đl�ԋ���ƌ������Ƃ���ԑ厖�ɍl���Ă��܂��B�v |
|
��8 |
|
A����@�u�����搶�Ə��w�S�N���̍����߂ďo����āA�ŏ��͂Ƃ��Ă��|���ăI�[�P�X�g���ɍs���̂�����������ł����ǁA���͂��������y����D���ɂȂ��āA�l�ԓI�ɂ������ł��āA�����g���肪�Ƃ��������܂��h�ƌ����@��Ȃ��̂ł��̏����āA�g�����搶�������肪�Ƃ��������܂��B���ꂩ�����낵�����肢���܂��B�h�v�i���K��̌��n���i���y�j�������n�߂�B�@�j |
|
��9 |
|
���K���i�i���W�̉��y�����̂܂܌��n���ɂȂ����Ă���j |
�d�w�I�ȍ\���̗�Ƃ��āA�w����X�e�[�V�����x2004�N�x��X��u����!�X�̃R���T�[�g�`��t�����N�����I�[�P�X�g���v�̈ꕔ�������i�\�P�j�B���̃V�[���̎��ۂ̎�ނł́A�܂��A�I�[�P�X�g���̒c���̍��Z���R���ɃO���[�v�C���^�r���[�����A���ɃI�[�P�X�g���̎w���ɂ������Ă��鉹�y�ē̍����O�q�搶�ɒP�ƂŃC���^�r���[�����B�����āA�����̑f�ނ��A�ҏW�̒i�K�ňȉ��̂悤�ɐςݏd�˂��i�d�w�������j���̂ł���B
���P���灔5�̉f���ŁA���Z���R���iA�`C�j���A�߂��߂��C���^�r���A�[�ɓ�����BA����AB����AC���ꌾ���q�ׂ����ƁAA����̔����ɂ��ǂ�AA�������搶�ɂ��Č��y�����Ƃ���ŁA�f���́��U�̗��K���i���Љ��B���̉f���́A�I�[�P�X�g���̗��K���i���ʂ��Ă��邪�A�y��̉��͕������ɁA�����搶�̃C���^�r���[�̑O�������̌��t���d�Ȃ��Ă���B�����搶�̌㔼�̔����́A���V�̍����搶�̌��p�ł���B
���Ɂ��W�ŁA�Ăэ��Z��A����̔����ƂȂ�BA����́A���̃J�b�g�ŃC���^�r���[�ɓ����Ȃ���A�����搶�ɂނ��āA�u�����g���肪�Ƃ��������܂��h�ƌ����@��Ȃ��̂ł��̏����āE�E�E�B�g�����搶�������肪�Ƃ��������܂��B���ꂩ�����낵�����肢���܂��I�h�B�v�Ə����Ƃ��悤�ɁA�������傫�Ȑ��Ō����ē���������B���́��W�̃J�b�g�̓r������A���K���i�̉��y�������n�߁A���X�ł́A���̉��y���w�����鍲���搶�̕\��A�����āA���������K���i�̖͗l�ւƑ����Ă����B
���̃C���^�r���[�ł́A�C���^�r���[�Ɨ��K���i�̉��Ɖf�������݂ɑg�ݍ��킳��AA����̔����ƁA�����搶�̔��������݂ɑg�ݍ��킳��Ă���BA����̔����i���Q�C���T�A��8�j�́A�ЂƂ̃C���^�r���[�Ƃ��ĘA�����Ă������̂����A���ꂪ�����A�r���ɗ��K���i�⍲���搶�̉f�������܂�邱�ƂŁA�{���̎��Ԑi�s�͉��Ă��邱�ƂɂȂ�B
�����̎�ނɂ����āA���Z��A�`C����ƍ����搶���C���^�r���[�����͓̂������������A���Ԃ͕ʁX�Ȃ̂ŁAA����̔����������搶�͒��ڕ����Ă��Ȃ��BA����͂��̏�ɂ͂��Ȃ������搶�ɑ��āA���ӂ̌��t���Ă��邪�A���������ԑg�ł͍����搶�ɑ��ē`��������̂悤�ɕҏW����Ă���B�܂�ԑg�̒��Ől�דI�ɑΘb�������Ă���̂ł���B���̂��ƂŁA���Z���������搶�̌������������������w���ւ̊��ӂ⑸�h�̔O������Ă��邱�Ƃ�������A���̊��ӂ̊�����킳��A���̃I�[�P�X�g���̊������D�ꂽ�l�ԋ���̏�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������҂Ɉ�ۂÂ�����Ǝv���B
�C���^�r���[�̏d�w�I�\���Ƃ́A���̂悤�ɁA���W�����f�ނ�ςݏd�˂Ă������ƂŁA�����Ɍ��킳�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��Θb�⊴��̌𗬂�\������i�\������j���ƂŁA���̓��ʓI�Ȑ^����^�����яオ�点�邱�Ƃ��ł���A����߂Ĕԑg�I�ȕ\�����@���ƌ����邾�낤�B
�����炭A����Ɍ��炸�A�����ɂ͑��҂ւ̊��ӂ̌��t�ȂǏƂꂭ�����Č����ɂ������̂����A�C���^�r���[�Ƃ��������邱�Ƃɂ���āAA����u���肪�Ƃ��������܂��v�Ƃ������t��������o���̂��ƌ����悤�B�C���^�r���[�ɂ���Ă��̂悤�Ȕ����������o�����Ƃ��A�����̎��Ԃ�ꏊ�̊W���āA���̑f�ނ��d�w�I�ɍ\�����Ă��܂����Ƃ��A�l�דI���邢�͍�דI�Ȃ��̂��Ƃ�����B�������A�����ŕ`����Ă���̂͋��U�Ȃǂł͂Ȃ��A�ނ���A�Ƃ�����Ό����̐����̏�ł͕\��ɂ����^����^�����A�ԑg�C���^�r���[�ɂ���Č@��N�����ĉ��������P�[�X���Ƃ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����낤���B
2.4�@�C���^�r���[�̕ҏW�Z�@
���݂̃m�����j�A�ҏW�@�ł́A���x�ŕ��G�ȏ������\�ł��邽�߁A�Z�I���Â炵�ĕ��G�ȕҏW�����Ă��܂����������A���̂悤�ȃe�N�j�b�N��M���邾���ł͂Ȃ��A�b����̔������m�[�J�b�g�ł�������ƌ����A���������ق����悢�ꍇ���������B��̑I��������Z�I�������Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�厖�ȕҏW���@�̂ЂƂł���B
�b����̌��t�̂����ɁA�ʂ��f����킹�邱�ƂŁA�b���̓��e����̓I�ɕ⋭���Ă����Ƃ������@�͌��ʓI�ȕҏW���@�Ƃ��đ��p����Ă���B�ԑg�̖ړI����e�ɂ���ẮA��l�̐l���̃C���^�r���[�𒆐S�ɂ��āA���̕��@�Ŕԑg�S�̂��������邱�Ƃ��ł���B�m�����j�A�ҏW�@�ɂ���ẮA���́u��ɔ킹��f���v��u���ꏊ���A�C���T�[�g�g���b�N�Ə̂�����A���̋Z�@���u�f�����C���T�[�g���飂Ƃ������Ƃ�����B
�C���T�[�g�̋Z�@�́A�W�����v�V���b�g���B���ꍇ�ɂ������Ηp������B�ԑg�C���^�r���[�̕ҏW�ł́A�����T�C�Y�ƃA���O���Ől�����B�e���Ă���J�b�g�i�Z�C���T�C�Y�j�̓r���Ŕ����̕s�v�ȕ�������菜���A�O��̃J�b�g�����̂܂܂Ȃ���ƁA�b����̕\��⓮�삪���ł��܂��i���삪�W�����v���Ă��܂��j��ԂɂȂ�B
���o�I�ɕs���R�ȃV���b�N�������邽�߁A���̕����������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA������̑��̃J�b�g��ʂ̉f�����C���T�[�g����i�����́A�b����̌��t���A�����Ă���悤�ɕҏW���Ă����āA�f���݂̂�킹��j�ƁA�����҂͔������ҏW����Ă��邱�ƂɁA�قƂ�NjC�����Ȃ��B
���������Z�I��p�����ɁA�W�����v�V���b�g�����̂܂܌����āA�ҏW�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ������҂ɊJ�����邱�Ƃ����邵�A�W�����v�����Q�̃J�b�g���A�����Z�����Ԃ点�ĉ�ʓ]������i�f�B�]���u����j���ƂŁA���̃V���b�N�������ł��a�炰�悤�Ƃ�����@������B���̂悤�ȍו��ɂ�����\���̑���ɂ���Ă��A�ԑg�������ہA���킢�⌻�����Ƃ��������̂��قȂ��Ă�����̂ł���B
�f���ԑg�́A���i���t�A���A���y�j�Ɖf���ɂ���č\������Ă��邪�A�S�̓I�ȗ����N���̈�ۂ͉��ɂ���ĉ��o����Ă��邱�Ƃ������B���y�̓���I������ʓ]���ɂ��킹����A��ʓ]���ɍ��v�������̏����������Ȃ��ƃX���[�X�Ȉ�ۂ��āA��i�Ƃ��Ă̊����x�����܂邱�Ƃ������B���y�̏I������ʓ]���ɍ��킹��ɂ́A�����f�B�[�̏��߂�P�ʂƂ��ĉ��y�̍Đ����Ԃ�L�k������e�N�j�b�N���K�v�ƂȂ邱�Ƃ�����B���̂悤�ȉ������̍I�ق���i�̊����x�̈�ۂ�傫�����E����̂ł���B
�ԑg������������i�K�̕ҏW�ł́A���ʂ≹���𐮂��A�������ɂ������́A�����t�B���^��p���ĕ������₷������Ȃǂ̍�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�a�f�l����ʉ��ƁA�i���[�V������C���^�r���[�̐��̑傫���̃o�����X�𐮂���B�A�}�`���A�̍�i�ł́A�a�f�l����ʉ����̉��ʃ��x�����������āA�l�Ԃ̌��t���������ɂ����Ȃ邱�Ƃ�����B�ԑg�̍���́A���x���ҏW��Ƃ����Ă���ԂɁA�쒆�l�����������Ă���̂��Ɋ���Ă��܂��Ă��邪�A�����҂ɂ͂悭�������Ȃ��Ƃ������Ƃ�����B�w�b�h�z���Ȃǂ̉��̕���\�������@��ł͂Ȃ��A��ʓI�ȍĐ����u�ŊG�Ɖ����Đ����ă`�F�b�N���Ă݂邱�Ƃ��K�v�ł���B�����҂��X�g���X�������邱�ƂȂ��A�ԑg�̘b���̗���ɏ���Ă�����悤�ɁA�����҂̖ڂƎ��ƐS�Ŕԑg�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ҏW�̒i�K�ŁA�����i�e���b�v�j���d�˂邱�Ƃ��ł���B�O����̔����ɓ��{�ꎚ����������A�������ɂ������t�������ŕ������A�����̗v�|��v����A�ȒP�ȗp�����������Ȃǂ̏ꍇ������B
�C���^�r���[����̑I�����ĕҏW����ꍇ�A�c��ȃC���^�r���[�̂ǂ̕�����I�ׂ悢���́A�f���f�ނ����Ă��邾���ł͂Ȃ��Ȃ����f�����Ȃ����Ƃ������B���̂悤�ȏꍇ�́A�ʓ|�ł��A�C���^�r���[�̑S���������N�����A�����ɂ�����ԂŕҏW���@���l���������A���ʓI�ɂ������I�ŁA�j�S�����ҏW���s�����Ƃ��ł���B�C���^�r���[�̑S�������N�����́A�v���ł��A�A�V�X�^���g�f�B���N�^�[�Ȃǂ����[�e�B�����[�N�Ƃ��čs����{�I�ȋƖ��ŁA�^����ׂ����@�ł���B�������Ĕ����̗v����I�яo���A�܂�������t���b�v���p���ă|�C���g���������Ď����Ȃǂ̂��Ƃɂ���āA�����҂��C���^�r���[����藝�����₷������H�v���K�v�Ȃ̂ł���B
�R�D�ԑg�C���^�r���[�̕��@
3.1�@�ԑg�C���^�r���[�̌`��
�@
�����܂Ō��Ă����悤�ɁA�ԑg�C���^�r���[�́A���̑O��ƂȂ�ړI��g�g�݁A�ԑg�̍\������j�Ȃǂɂ���āA���܂��܂Ȃ�����������B�����āA�ԑg�゠�邢�͌���ł̕K�v���Ȃǂɂ���āA�C���^�r���[�͊���̌`�Ԃ��Ƃ邱�ƂɂȂ�B��̓I�ɂ́A
�@������Ƙb����̐l��
1��1�̑Βk�`����A�����肪�����Řb���肪�����̉�����A�����肪�����Řb���肪�����̃O���[�v�`���Ȃǂ�����
�A�C���^�r���[�̒���
�����O�C���^�r���[�ɂ���Ă���b����ɂ��킵�����낤�Ƃ���悤�ȏꍇ������A�X���ő����̐l�X���炲���Z���R�����g��悢�ꍇ������
�B�C���^�r���[�̏ꏊ
����Ŋ������̐l�ɂ��̏�Řb�����ꍇ������A�C���^�r���[�̏ꏊ���ʂɃZ�b�e�B���O���čs�Ȃ��ꍇ������B�C���^�r���[�̏ꏊ�����̂��Ƃ�����A�l�Ԃ��J�������ꏊ���ړ����Ȃ��炨���Ȃ����Ƃ�����
�C�J�����i�ƃ}�C�N�j�̑䐔
�P��̃J�����ł����Ȃ��̂��A�����̃J������p����̂��A�}�C�N�͂P�{���A�������j
�Ȃǂ̂��Ƃ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̂ق��ɂ��A�ԑg����̓�����\�Z�A�@�ނ�X�^�b�t�A�����Č���̎��͂̏�A�V���ړ��ɂƂ��Ȃ����܂��܂ȗv�f�����̂��ƂɁA�K�Ȕ��f�ƑI���������Ȃ��Ȃ���A�ԑg�C���^�r���[�͎��{�����B
3.2
�@�ނ̑I���Ǝg�p���@
�ԑg�C���^�r���[�̖ړI�ƌ`�Ԃɂ����āA�K�ȋ@�ނ��������A�C���^�r���[�ɗՂނ��ƂɂȂ�B�J������}�C�N�ɂ��Ă̐������m���Ƒ�����@��m��A���O�ɏ\���ȃe�X�g�Ɨ��K���s���Ă������Ƃ��K�v�ł���B
�ԑg�C���^�r���[�ł́A��ʂɃr�f�I�J�����ɓ������ꂽ�}�C�N�ł͂Ȃ��A�O���}�C�N���g���Ęb����̔����𖾗ĂɂƂ炦�A�L���P�[�u���܂��̓��C�����X�ŁA�J�����̊O���������͂ɐڑ����Ď��^����Ƃ������Ƃ����ʂł���i�̂̉f��J�����ł͎B�e�Ƙ^���̃V�X�e���͕ʁX�ł��邱�Ƃ������������A���݂ł��B�e�E�^���V�X�e�����ʂɂȂ��Ă��邱�Ƃ͂���B���̏ꍇ�A�ҏW�̍ۂɉf���Ɖ�������v���邽�߂ɓ������Ƃ邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�f��B�e�ɂ�����g�J�`���R�h�͉f���Ɖ����̈�v�_���L�^���ē������Ƃ邽�߂̍H�v�̈�Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂ł���B�j
�厖�ȃC���^�r���[�ł́A�K���w�b�h�z�����p���āA���������ʂƉ����Ř^������Ă��邱�Ƃ��m�F���A�܂��C���^�r���[�̌�ōĐ����Ă݂āA�`�F�b�N���Ă����ׂ��ł���B
�b����̔����𖾗ĂɂƂ炦�邽�߂ɂ́A�^���@�ނ̎�ނ���ɂ��Ă悭�m��A�������g���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�g�p����}�C�N�̑I���́A�ړI��ɂ��킹�āA
�@�}�C�N�̎�ނ��
�L���}�C�N�����C�����X���A�_�C�i�~�b�N�^���R���f���T�^���A���w�������P��w���������w�������Ȃ�
�A�d���̕K�v�̗L���₻�̋������@
�d�r���v���O�C���܂��̓t�@���g�����ȂǁA�d�r�̌^��K�i�Ȃ�
�B�`��
�莝���^�A�^�C�s���^�A���^�A�e�[�u���}�C�N�A�K���}�C�N�Ȃǁj��ݒu���@�i�}�C�N�z���_�[�a�Ȃǁj
�C�v���O�̌`���ڑ����@
���t�^���s���t���A�ڑ����@�͕W���v���O���A�w�k�q�L���m�����A�X�e���I�~�j���Ȃ�
�D�t���i
���h�≄���R�[�h�A�ڑ���ϊ��̂��߂̃v���O�A�w�b�h�z���Ȃǁj
�Ȃǂ̓_���m�F���A�K�v�Ȃ��̂���������B�܂��A����ɐڑ������J�����̑��̐������ڑ��Ƒ���̕��@�i�������͂̐�ւ���A�`�����l���̎g�p���@�j��A���ʃ��x���̒������@�i�I�[�g���}�j���A�����j���m���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�����̃}�C�N��p���ă~�L�V���O����ꍇ�̓~�L�T�[���A������ɕ����̃J�����ɕ��z����ꍇ�́A���z�킪�K�v�ƂȂ�B�C���^�r���[�����J���_��Ȃǂ̏�ōs����ۂ́A�����̊g���V�X�e������̃��C���o�͂��J�����ɐڑ����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�ꍇ������B��ނ̂��߂Ƀ��C�����X�}�C�N���g���ꍇ�ɂ́A�C�x���g���Ŏg���Ă���̂Ɠ������g�����g���ēd�g�������邱�Ƃ�����̂ŁA���g����ύX����Ȃǂ̑Ή����K�v�Ȃ��Ƃ�����B
�@�ނ̎g�p�ɍۂ��ẮA�P�Ȃ鐫�\��̒m�������A�}�C�N�̈������A�����ւ̋߂Â����i�p�x�⋗���j�A���̂ӂ��������╗�؉��ւ̑Ώ��̕��@�A�^�C�s���}�C�N�̍ۂ̃P�[�u���̉B�����Ȃǂ̋�̓I�Ō����I�Ȏg�p�@�̏K�����K�v�ł���B�C���^�r���A�[��1�{�̃}�C�N���A�����Ƙb����Ɍ��݂Ɍ����đΘb�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������A���̂悤�ȃ}�C�N�̎g�����Ȃ��́A���O�ɗ��K���Ă������ق����ǂ��B����Ă��Ȃ��ƁA�C���^�r���A�[���A���̃}�C�N�̌�����ς��邱�Ƃ�Y��邱�Ƃ����邩��ł���B
���\�̂悢�@����w���ł���Ȃ����ɂ��������Ƃ͂Ȃ����A��������X�^�b�t���C���^�r���[�̌���Ő������v���Ɏg�����Ȃ��邱�Ƃ���ł���B�����^�тɍۂ��Ă̋@�����A�̏Ⴕ���ꍇ�̔����i�\���i�Ȃǁj�A�_�����|�̗�s���ʒu�ւ̎��[�A�Y�ꕨ��Ȃ��������Ȃ��悤�ɋ@��ɕ\����\��A���Q�i���X�g�����Ȃǂ̂��Ƃɂ��z�����āA�V�X�e�}�e�B�b�N�ȉ^�p���s�����Ƃ��K�v�ł���B�R�l�N�^�[��ڑ�������P�[�u���������������肷��ۂ̗͂̉����Ƃ��A�P�[�u���̂܂����ȂǁA������Ƒ̂Ŋo���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ���������B
�c�̊����̏ꍇ�ɂ́A�����ɌŗL�ȉ^�p�K����w���ȂǁA������̃`�[���̕����Ƃ��č\�z����`�������m�E�n�E�����낤�B�ԑg����̔\�͂ɂ́A�}�j���A���ɖ������ł��A��ʉ������悤�Ȃ��̂����邪�A�K���������������ꂸ�A�c�̂��قȂ���[������@���قȂ�悤�ȌʓI�ňÖْm�I�Ȃ��̂�����B���̑o���̂��Ƃ��ӎ����āA�`�[���Ƃ��Ă̏�����ӎ������L���A�����납�珀�����P�����Ă������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���B
3.3
�C���^�r���[�̃X�^�b�t
�ԑg�C���^�r���[�����{����ɍۂ��āA����̑��A���Ƀf�B���N�^�[�ƃJ�����}���i���˂Ă��邱�Ƃ��������낤�j�ƃC���^�r���A�[�i������j�̊Ԃőł����킹���Ă����ׂ����ƂƂ��āA���^���X�^�[�g����ۂ̃^�C�~���O�ƍ��}�i�L���[�j�̖�肪����B���̑ł����킹���\���łȂ��ƁA�f�B���N�^�[���u�X�^�[�g�v�ƌ���������ɃC���^�r���[���n�܂��Ă��܂��A�ҏW�ɕK�v�ȊԂ��Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ�������A�J����������Ă��Ȃ��̂ɁA�b�����n�܂��Ă��܂����肷��B
�C���^�r���[�̃X�^�[�g�̃L���[�̕��@�́A
�@�J�������X�^�[�g���A�m���ɘ^�悪�X�^�[�g�������Ƃ��i�����̃J�����ł͘^�惉���v���_�����ăJ�E���^�[�����Z���n�߂�j�m�F���āA�J�����}�����f�B���N�^�[�ɁA�u�J�������܂����v�Ɠ`����B
�A�f�B���N�^�[�́A�w���o����5�b�O�i�Ȃ���3�b�O�j���C���^�r���A�[�Ɏ����Ă���J�E���g�_�E�����A�u�R��Q�E�v�Ƃ��������A�u�P�v�𐺂ɏo�����ɁA�w�����̓���ȂǂŃL���[���o���B
�B�C���^�r���A�[�́A�Ō�́u�P�v�𐺂ɏo�����ɃJ�E���g���Ă���A�C���^�r���[���X�^�[�g����B
�Ƃ����悤�ɂ���̂��A�������₷�����낤�B
�C���^�r���[�����{����ۂɂ́A���S�X�^�b�t���A���̂ق��̊W�҂��C���^�r���[�ɏW�����A���������Ă�Ȃǂ̏�Q�ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͂������A�S�������ӂ���ԓx�ŗՂ�ŁA�b���₷�����͋C�����肾�����Ƃɋ��͂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�X�^�b�t���m�����ǂ��y�������͋C�������Ă��Ȃ���A�b����͐S���₩�ɘb���Â炢�B�ԑg����̖ړI����e���X�^�b�t�ɋ��L����Ă��āA�`�[�����[�N�̂Ƃꂽ�s�����������Ƃ��A�ԑg�C���^�r���[�ɂƂ��Ă͕K�v�Ȃ��Ƃł���A���̂悤�ȃX�^�b�t�S���̐S�̂�������A�ԑg�ɂ����������̂ł���B
3.4
�ԑg�C���^�r���[�̉f��
���悢�ԑg�C���^�r���[�̏��́A���́u��́v�ƂȂ�l�i�C���^�r���[�ɓ�����l�j���悭�ʂ��Ă��邱�ƂƂ��厖�ł��邪�A�����ɁA���́u�w�i�v�ƂȂ���́A�Ȃǂ������ɁA�悭�`��邱�Ƃ��A���̌��ʂ����߂�B
�܂�u��́v�Ɓu�w�i�E�v���A�K�x�ȃo�����X�̂��Ƃɒ���K�v������B
|
�ԑg�C���^�r���[�ɋ��߂���Q�̗v�_ �@����@�F�l���̕\��悭�킩��A�b�̓��e�Ɏ����҂̈ӎ����W���ł��邱�ƁB�i���̂��߂ɍ\�}�����肵�Ă��āA�s���g��I�o�����������Ɓj �A�w�i�E���@�F�f���̓C���^�r���[�������Ȃ��Ă�����͂̏i�w�i�j���A�ł��邾���I�m�ɓ`���邱�ƁB |
���̂Q�_�����悭���������邱�Ƃ��A�f���C���^�r���[�Ƃ��Ă͑�ł���B
�ȉ��́A������x�܂Ƃ܂��������̘b���A������x�Z�b�e�B���O���ꂽ�ōs���P�[�X��z�肵�āA�����Ƃ���{�I�Ȏ����ɂ��āA���ӂ��ׂ��_���܂Ƃ߂Ă݂�B
|
�ԑg�C���^�r���[�������Ȃ��ꍇ�̗��ӓ_ �@�ꏊ�Ɣw�i �A���ӂ̉� �B�t�H�[�J�X �C�Ɩ��ƘI�o �D�A���O���ƃT�C�Y �E�l���̈ʒu�Ɗ�i�����j�̕��� �F�ו��ɂ�������z�� �G�G�X�^�u���b�V���O�E�V���b�g |
�@�ꏊ�Ɣw�i
������Ƙb����̔w�i�ƂȂ���̂��A�ԑg�̖ړI�ɍ��v���Ă��āA���͂̏��킩��₷���ꏊ��w�i��I�ԁB�Ⴆ�A���镔���̂Ȃ��ōs���Ă���C�x���g�ɂ��ĊW�҂̘b�����ꍇ�A�����̕ǂ�w�i�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�ǂ̑O�ɃJ������u���āA���������n�������ɃJ�������ނ��āA�����ɐl���������Ƃɂ���āA�l���Ǝ����̏��ɍ\�}�Ɏ��߂�悤�ɍl����̂���{�ł���B�i���̂悤�ȏꍇ�̓C�x���g�̍Œ��ɃC���^�r���[�����s���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̎��{�̃^�C�~���O�ɂ��āA�b����̗����Ƌ��͂��s���ɂȂ�B�j
�\�}�̂Ȃ��ł́A�w��ɂ�����̂Ɛl���Ƃ̏d�Ȃ�����K�ȏ�ԂɂȂ邱�Ɓi�Ⴆ�A�l���̓��̏�ɓd���������Ă���悤�ȍ\�}�ɂ��Ȃ��Ȃǁj��A�]�v�Ȃ��̂�l���r������ʂ��Ă��Ȃ��悤�ɂ���B�w��ɋ���K���X�������āA�J������X�^�b�t�����˂��Ă��܂��Ƃ���A�J�����_�[�⎞�v���ʂ��Ă���Ƃ������ӂ��K�v�ł��낤�B�w�i�ɂӂ��킵���ꏊ��T���Ĉړ�������A���̂Ƃ������w�i�ɃC�x���g�̊Ŕ�|�X�^�[�������Ă����肷��ȂǁA�B�e����ł̓X�^�b�t�̋@�]�����������s�����傢�ɋ��߂���B
�A���ӂ̉�
�ł��邾�����͂̑����̂Ȃ��ꏊ��I�Ԃ��Ƃ���{�����A���͂̏��ɂ���Ă̓��A���e�B�������Ƃ����ꍇ������A���̃o�����X���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�w�i�ɉ��y������Ă���悤�ȏꍇ�A�ҏW����Ɖ��y���r��Ĕ�肷�邱�ƂɂȂ�̂ŁA�ł��邾�����y�̂Ȃ��ꏊ��T������A���y���~�߂Ă��炤�悤�Ɍ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�p�\�R�����̋@�B������ł��镔���ŃC���^�r���[����ꍇ�́A���̏�ł͂��܂葛���Ƃ��ċC�ɂȂ�Ȃ��Ă��A���ƂōĐ����Ă݂�Ɣ��Ƀm�C�Y���傫���������邱�Ƃ�����̂ŁA���ӂ��K�v�ł���B�m�����j�A�ҏW�@�̉����t�B���^�@�\���g���āA�������܂������g�����J�b�g����ȂǁA�����₷�����ʉ����ɐ������Ƃ��K�v�ƂȂ邱�Ƃ�����B
�B�t�H�[�J�X
�l���Ƀs���g�������Ă��邱�Ƃ͑�ȗv���ł���B�r�f�I�J�����̃I�[�g�t�H�[�J�X�@�\���g���Ă���ꍇ�A�C���^�r���[�̓r���ŁA�l���Ɣw�i�̊ԂŃs���g���ړ����Ă��܂����Ƃ�����̂ŁA�ł��邾���}�j���A���t�H�[�J�X�̋@�\��K�Ɏg�����Ƃ��]�܂����B�w�i�Ƀ^�C���̕ǂ⏑�I�ȂǁA�����I�ȃp�^�[���������ꍇ�ɂ́A�I�[�g�t�H�[�J�X�@�\���w�i�Ƀs���g�����킹�Ă��܂��₷���̂Œ��ӂ�v����B�}�j���A���t�H�[�J�X�̏ꍇ�A�܂��l���̖ڂ̂�������ő�ɃY�[���A�b�v���āi�ő�]���ɂ��āj�蓮�Ńs���g�����킹�A���̈ʒu�Ƀt�H�[�J�X���Œ肵�Ă����āA�K�v�ȍ\�}�ɂ��ǂ��Ƃ������Ƃ��s���g���킹�̊�{�ł���B�]���ɂ��邱�ƂŁA��ʊE�[�x�i�s���g�������Ă���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���͈́j���Ȃ�A���m�ȃs���g���킹���\�ƂȂ邩��ł���B
�C�Ɩ��ƘI�o
�l���̕\��킩��₷���悤�ɁA�K�Ȍ����Ől�����Ɩ�����Ă���ꏊ��I�Ԃ��Ƃ��]�܂����B�K�v�Ȃ�ΎB�e�p�Ɩ���p���邪�A�����ł́A���C�g��b����Ɍ�����̂ł͂Ȃ��A�V���ǖʂȂǂɌ����A���̃o�E���X���i�͂˂����������j�ɂ��_�炩�����Řb������Ɩ�����ȂǁA�H�v����B
�ŋ߂̃r�f�I�J�����͊��x�������̂ŁA���̏�̏̌����ŎB�e�\�Ȃ��Ƃ������A�Ɩ����g���Ęb������ْ������Ȃ��ق��������ꍇ������B�������A�F���x��u�������ł̃t���b�J�[�Ȃǂɂ��Ă͒��ӂ��K�v�ł���B�t���ɂȂ��Ă��Đl���̕\��A�ɂȂ�ꍇ�́A�J�����̋t�����}�j���A���I�o�̋@�\�A�Ɩ���t�i���˔j�Ō���₤�A���邢�̓J�����Ɛl���̈ʒu�������ς���Ȃǂ��đΉ�����B�t���̏�Ԃ͉��O�����łȂ��A���┒���ǂ��w�i�ɂȂ�ꍇ��A�V��̏Ɩ��Ƃ̈ʒu�W�ɂ���Ă�������̂ŁA�I�o���Ɩ����K�v�ƂȂ�B�����̏ꍇ�ł��A��ɋɒ[�Ȓ��˓������������Ă���ƕs���R�Ȃ��Ƃ�����A����ῂ����Đl�����ڂ��ׂ߂Ă��܂����Ƃ�����̂ŁA���A�ɓ�������A���t�����݂̕������Ƃ��āA�i����J�����背�t��p����ق����K�ȏꍇ������B
�l���ɉ��₩�Ȍ������������Ă���ꍇ�ł��A�����I�o�̍i��l���R���̂P����Q���̂P�i���x�A�i����J�����ق����l���̊�𖾂邭�Y��ɎB��邱�Ƃ������̂ŁA�}�j���A���I�o�̑�����@���悭�������ė��K���Ă������ق����悢�B�������A���O�ŃC���^�r���[�����Ă���ƁA�_�̓����œ��������ω����Ă������Ƃ������āA����ɉ����ĘI�o��ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B�ԑg�̓��e�ɂ���ẮA���ɋÂ����Ɩ��̂��ƂŁi�Ⴆ�ΐ^���Âȕ����̂Ȃ��ŁA�l���ɃX�|�b�g�Ɩ����������Ă���悤�ȉ��o�j�A�C���^�r���[�̓��e�����ۗ�������悤�ȏꍇ�����邾�낤�B
�D�A���O���ƃT�C�Y
�J�����̍����́A��ʑ̂ƂȂ�l���̖ڂ̍����Ƃقړ����ɂ��邱�Ƃ����R�ł����{�����A�l���̓����ɔ���悤�Șb���̏ꍇ�́A�J������Ⴍ�����ă��[�A���O���łƂ炦�邱�Ƃŕ��͋C���o�邱�Ƃ����邵�A���Ƃ��ĕK�v�Ȕw�i���l���̔w��ɍL�����Ă���悤�ȏꍇ�ɂ́A�n�C�A���O���ɂ����ق����ǂ��ꍇ������B
�b����̕\����Ƃ炦��ɂ́A��ʓI�ɃE�G�X�g�V���b�g����o�X�g�V���b�g�A�b���̓��e�ɂ���Ă͂���ɃA�b�v�ɂ��邱�Ƃ��K�ƂȂ낤�B�C���^�r���[�͊�{�I�ɎO�r�ɃJ�����𐘂��āA�t�B�b�N�X�ŎB��ׂ��ł���B�������b����̊�͊�{�I�ɂ͒��������A��≡��ƂȂ邱�Ƃ������ŁA�����̐�̋�ԁi�b���Ă��鑊��̂�����̋�ԁj�̂ق�������B�ڂ̍����������������̂�≺���炢����{�Ƃ��邱�Ƃō\�}�����肷�邱�Ƃ������B�o�X�g�V���b�g�̏ꍇ�A�l���̓��̏�Ɏw�Q�`�R�{���̋�Ԃ��Ƃ�邭�炢�ƂȂ낤�B���S�҂́A�����\�}�̐^�ɐl���̊��u���Ă��܂��X�������邪�A�l���̓���ɖ��p�ȋ�Ԃ��ł��Ă��܂��̂ŁA�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���R�Ȃ���l���̕\��⎋���̕����A�p����g�U��ɂ���Ă��\�}�͕ω�����B���������h�ꂪ�����܂�͈͂ł̃o�X�g�V���b�g���t�B�b�N�X�ŎB�邱�Ƃ��ł��m���ȍ\�}�ł��邪�A�o�X�g�V���b�g���A�b�v�ɂ��Ă���ꍇ�ɂ́A�t�B�b�N�X�ł���Ȃ���A�l���̓����ɏ]���āi�t�H���[���āj�p����e�B���g�Ȃǂ̃J�������[�N���s�����Ƃ��K�v�ȏꍇ������B
�f���C���^�r���[�́A�l���̘b���̓��e�Ɏ����҂��W���ł���悤�ɁA�\�}�̒��̏��������ɐ������Č����邩����Ȃ��Ƃł���B�K���������G�ȃJ�������[�N�������Ȃ��K�v�͂Ȃ����A�v���̃J�����}���́A�ꌩ�V���v���Ɍ�����\�}�̂Ȃ��ɂ��A���i�Ɩ��j��w�i�A���ߊ��i�p�[�X�y�N�e�B�u�j���ʊE�[�x�ɑ��钚�J�Ȕz�������Ă�����̂ł���B�P���ƌo����ς�ŁA���ǂ��f�����B��w�͂��͂炤�K�v������B
�E�l���̈ʒu�Ɗ�i�����j�̕���
������Ƙb����̓�l�̓o��l���̑Θb���̃J�����Ŏ��^����ꍇ�A�J�����P�͕�����̃o�X�g�V���b�g�A�J�����Q�͘b����̃o�X�g�V���b�g�A�J�����R�͓�l�̐l���Ǝ��͂̏����߂��t���t�B�M���A�Ȃ��������O�V���b�g�Ƃ����悤�ɖ����S���邱�ƂƂȂ�B���̂悤�ȏꍇ�A�b����ƕ�����́A�Ζʂ����ʒu���Ƃ��ė��i����j���Ƃ��ł��A���݂��̊�𐳖ʂɌ��Ȃ���Θb���邱�Ƃ��ł���B�J�����̈ʒu�ɂ���āA�\�}�̕Ћ��ɕ�����̌����킸���ɓ���āi�i���āj�A�b����̕\����Ƃ炦��Ƃ������Ƃ��ł���B�i�������A�C�}�W�i���[���C�����z���ăJ������u�����Ƃ́A������Ƙb����̃J�b�g�̎����̕�������������Ȃ����ʂƂȂ�̂Ŕ�����ׂ��ł���B�j
�J�������P��̏ꍇ�A�ŏ��ɓ�l�̃c�[�V���b�g���B�e���A��������J�������~�߁A�J�����|�W�V������\�}��ύX���āA�����肠�邢�͘b����̊���o�X�g�V���b�g�ŎB��Ƃ����悤�ɁA���^�𒆒f���Ȃ���B�e���A�ォ�畡���̃J�����Ŏ��^�������̂悤�ɕҏW���邱�Ƃ��ł���B�C���^�r���[�𒆒f�����ɎB��ɂ́A��l�̐l���̕\��Ƃ炦�₷���悤�ɁA�J�������猩�ăn�̎��ɂȂ�悤�ȗ����ʒu�i����ʒu�j���Ƃ�A���݂����߂Ɍ���悤�ɂ��邪�A���̊p�x�Ƃ��ẮA�b����̂ق����A��萳�ʂɋ߂��p�x�Ƃ���ق����ǂ��B�\�}���A�ŏ��Ƀc�[�V���b�g����n�߁A�J�������~�߂邱�ƂȂ��A�b�̓W�J�ɏ]���āA�l���ɃY�[���A�b�v������A�p�������肵�Ęb��ǂ��Ă����Ƃ������@������B���̂悤�ȃJ�������[�N�́A�p���ƃe�B���g�A�Y�[�~���O���ɍs�����ƂɂȂ�A�@�ނ�Z�p�̖ʂł͓�����Ƃ�����̂ŁA���S�҂ɂ͑E�߂ɂ����B
�����ŁA�J�������P��ł���ꍇ�́A�܂��A�ŏ��̃c�[�V���b�g�ŁA�u��낵�����肢���܂��v�Ƃ����悤�ȃC���g���f���[�X���B���Ă����x�J�������~�߁A�J�����̍\�}��b����̃o�X�g�V���b�g�ɕύX���A�ăX�^�[�g�����Ă���A�C���^�r���[�̖{��ɓ���B���̌�̓J�������~�߂邱�ƂȂ��A�C���^�r���[���I���܂ő����ĎB��B���̌�ŁA�K�v������A�ĂуJ�����̍\�}��ύX���āA�u���肪�Ƃ��������܂����v�Ƃ����c�[�V���b�g�̃G���f�B���O�̂��߂̃J�b�g���B������A������̑��̕\����C���T�[�g�������ꍇ�́A���炽�߂ĕ�����̕\��⎿��A�����Ă���J�b�g���B�葫���A�ҏW�ō\������Ƃ������@�������I���낤�B
���ۂ̔ԑg�ł́A������̎p��K�v�Ƃ��Ȃ����Ƃ�����̂ŁA���̂悤�ȋZ�I��p���邱�Ƃ��Ȃ��A�b����̕\���������ƃt�B�b�N�X�ő����邱�Ƃŏ\���ł��邱�Ƃ������Ǝv����B���ۂɁA���܂�Z�I�I�ȃJ�b�g���������ĎB�e���邱�Ƃ́A���̂悤�ȎB�e���@�Ɋ���Ă��Ȃ��b����ɂƂ��Ă͈�a���̂���C���^�r���[�ƂȂ��Ă��܂����낤�B
�C���^�r���[�̓��e��ړI�������ł��Ă���A�Θb�̒��g�̐���オ���A�厖�ȕ����ɂ������������Ƃ���Řb����̕\��ɃY�[���A�b�v����ȂǁA�K�ȃJ�������[�N�ɂ���āA����ۓI�ȉf�������^���邱�Ƃ��ł���B��̕\������A���w�̂��������Ȃɂ�����Ă���Ƃ����ꍇ�ɂ́A���������炩����w��Ƀp���_�E�����邱�Ƃ����ʓI�Ȃ��Ƃ����邩������Ȃ��B���̏ꍇ�̏u���̔��f�͂�A�X���[�X�ȃJ�������[�N�̏K�n�ɂ́A�\���ȌP���ƌo�����������Ȃ��B
�\�}�̂Ȃ��ɕ�����Ƙb���肪���ꍇ�A��{�I�ɂ͉�ʂ̍����i����j�ɕ�����A��ʂ̉E���i���j�ɘb����i�Q�X�g�j�������Ƃ������B����̊��K�ł͂��邪�A��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A����̏��ŕύX���Ă悢�B�l���̔��̂킯�ڂ̕����Ŋ�̌������l���Ă��悢�B�܂��A������Ƙb����̐g�������傫�����āA�\�}��̃o�����X�������ꍇ�A�g���̒Ⴂ�l�ɓK���ȑ�ɏ���Ă��炤�Ƃ����H�v�����Ă��ǂ��i�c�[�V���b�g�ł��̑���ʂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��j�B���̂悤�ȋZ�@���̂��Ƃ��A���ăn���E�b�h�Ŋ������{�l�o�D�A�����M�̖��O���Ƃ��āu�Z�b�V���v�ƌĂԂ��Ƃ�����B�A�����J�l�o�D�Ƒ����M�������V���b�g�œK�ȍ\�}�ɔ[�܂邽�߂ɁA���삪�����Α�̏�ɗ���������ł���B�֎q�ɍ���ꍇ�������̍��������ƂȂ邱�Ƃ�����̂ŁA���ʂ̍������ς�����֎q��p����ƕ֗��ł���B
�F�ו��ɂ�������z��
�o��l�����X�q��T���O���X�����Ă��āA�\��Ƃ炦�Â炢�ꍇ�A�E������O���Ă��炤���Ƃ𗊂ނׂ����Ƃ�����B�����⓪����A�N�Z�T���[�A�p���₵�����ȂǁA���l���C�����ɂ������Ƃ��܂߂āA������ו��ɐ_�o��z��K�v������B�f���ł́A�i�e������\���������Łj�����������t�����N�ȑԓx�Ŏʂ낤�Ƃ���ƁA�����ȏ�Ɉ��Ԃ������悤�ȁA�s�^�ʖڂȑԓx�Ɍ����Ă��܂����Ƃ�����B��������b������A�p���ƕ����𐳂��A��⌘�����炢�̑ԓx�ŗՂނƁA�قǂ悢���Ƃ������B�����̋G�ߊ���O��̃J�b�g�Ƃ̓��ꊴ�ȂǁA�ԑg�S�̂̍\���̂Ȃ��ŗ��ӂ��ׂ����Ƃ�����B
���������X�^�b�t�̑�����̒����́A�Q�X�g�ł���b����ɑ��āA���s�����čs�����͂��Ă��炤�ׂ��ł���B�W���ɂ���ẮA�����o���ɂ������Ƃ������Ă��A�ǂ��Ȃ���Ԃ̂܂B���Ă��܂����͂����B�܂��A�K�����̏�ŕ����I�ɂł��Đ��`�F�b�N���s���A�Z�p�I�ȃ~�X�Ȃǂ�����A�ēx���Ȃ������s���K�v������B���ʓI�Ɏg���Ȃ��Ȃ���́A��������蒼���������ǂ��B���̂��߂ɂ��A�b����Ƃ̗ǍD�Ȑl�ԊW���\�z���Ă������Ƃ���ł���B
�G�G�X�^�u���b�V���O�E�V���b�g
�C���^�r���[�����^����ہA�b����ƕ�����̑Θb��ʂ����^���邾���łȂ��A���̎��͂�O��̑S�̓I�ȏ��킩��G�X�^�u���b�V���O�E�V���b�g�i�}�X�^�[�V���b�g�Ƃ������j���B�e���Ă������ƂŁA���悢�ԑg�\�����ł��邱�Ƃ������B�Ⴆ�A�C���^�r���[���s���錚���̊O�ς�A���̌����ɓ����Ă����C���^�r���A�[�̎p�Ȃǂ��B�e���Ă����Ƃ悢�B�G�X�^�u���b�V���O�E�V���b�g�́A��{�I�ɏꏊ�⎞����\�����郍���O�V���b�g�ł��邱�Ƃ��������A��t��g�t�ȂǁA�G�߂��ے�����ו����N���[�Y�A�b�v�ŎB���Ă������Ƃł��A�G�X�^�u���b�V���O�E�V���b�g�Ǝ������ʂŏ�ʓ]���ɗp���邱�Ƃ��ł���B�C���^�r���[�̎��ۂ̃A���O���̗���ʐ^1.2.�Ɏ����B
|
�ʐ^�P�@�c�[�V���b�g�̃C���^�r���[�̗� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w����X�e�[�V�����x���j |
�ʐ^�Q�@�E�G�X�g�V���b�g�̗� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w��������������x���j |
�S�D�ԑg�C���^�r���[�̓��e
4.1�@�C���^�r���[�̗v���Ƒg�ݗ���
�@�ԑg�C���^�r���[�̓��e���A���ǂ����̂Ƃ��邽�߂ɂ́A���̂R�̗v��������̂ł͂Ȃ����ƍl������B
|
�@�ԑg�C���^�r���[�̗v�_ �@�@�L�p�� �@�A��� �@�B�N�w�� |
�@�L�p��
�Θb�̓��e����L�p�Ő��m�ȏ�����邱�Ƃ����߂���B���̃C���^�r���[���������邱�ƂŁA�����炵���m����F���������A�Ȍ����_���I�ŁA�ԑg�̖ړI�ɍ��v���Ă��邱�Ƃ���ł���B
�A���
�L�p�ł��邾���łȂ��A�b����╷����̐l�Ԑ��⊴��`����Ă��邱�Ƃ����߂���B�߂��݂��сA�������`���C���^�r���[�A���邢�͕�����Ƙb����Ƃ̊ԂŘb����C���������ݍ����Ă��āA�����҂����S�L���ɂ�����C���^�r���[�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��厖�ł���B
�B�N�w��
�ʂ̎�����`���Ȃ�����A���̂Ȃ��Ɏ����҂��A��ʎЉ�ɕ~�����čl���邱�Ƃ̂ł���悤�ȓN�w���܂�ł��邱�Ƃ����߂���B�����̎����҂̓������A�������̃q���g�ƂȂ�悤�ȃL�[���[�h���^������悤�ȃC���^�r���[�ƂȂ邱�Ƃ��]�܂����B
�C���^�r���[�̕�����́A�ԑg�̖ړI�ɂ��������e���o�����Ƃ��K�v�ł���A���������Ă��炢�����̂��A����͂ǂ̂悤�Ȑl�ł��邩�����O�Ɋm�F���A�����p�ӂ��Ă����A�K�v�Ȃ�������茳�Ɏ��B
�ړI����e�ɂ���邪�A�������̎���ɂ��āA���炩���ߑ���ɂǂ̂悤�Ȏ�������邩��`���Ă����A��p�ӂ��Ă����Ă��炤���Ƃ��K�v�Ȃ��Ƃ�����B�܂��A�C���^�r���[�̃X�^�C����ԑg�̂Ȃ��ł̏������@�i���̌�̕ҏW��������̂��A�����Ȃ��̂��Ȃǁj�ɂ��Ă��悭�m�F���Ă����B���炩���ߗp�ӂ�������������łȂ��A����̉��悭�����āA�K�Ɏ����ς��Ă����Ȃǂ̗Ջ@���ς�����ł���B
�C���^�r���[����́A���܂��܂ȏ�����邪�A�킩�肫�������Ƃ�A�ق��Œ��ׂ�ςނ��ƁA���邢�͌��t�ŕ����������ł͂킩��Ȃ��悤�ȕ��G�ȃf�[�^�ȂǁA�C���^�r���[�Ƃ����`�ŕ������Ƃɂ͕s������������A�K�R�����������ɂ��ẮA�ʂɋ�̓I�ȉf����e���b�v�Ŏ������ƂƂ��āA�C���^�r���[�ł́A�l�Ԃ�����p��`���邱�Ƃɗ͓_���u�����ׂ��ł��낤�B
���̂悤�ȗv����O���ɂ����Ȃ���A��ʘ_�Ƃ��āA�C���^�r���A�[�́A�C���^�r���[�̂Ƃ肩���肩��O���ɂ����ẮA��̓I�ŌʓI�ȁA�����Đ��m�ȏ����Ƃ�A����ɁA�l�ԓI�Ȏv����C�����Ȃǂ̑��ʂɔ����Ă����A�C���^�r���[�̏I�Ղ�܂Ƃ߂̕����ł́A��ʂ̐l�X�ɂ��~���ł���N�w��A�L�[���[�h�ƂȂ錾�t���o������A���邢�͕�����̑�������A�L�[���[�h�ƂȂ�Ǝv����悤�Ȍ��t�𓊂������āA�|�C���g�������т�����悤�ɘb�����܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���悤�ɁA����┭����W�J���Ă����悤�ɑg�ݗ��ĂĂ������Ƃ��K���ł��낤�B
����̘b�����o�������łȂ��A������̊��z������A���ӓ_��^��_�����ɏo���āA���݂������Θb�����Ă������Ƃɂ���āA�����I�Ŋ����L���ȃC���^�r���[�̎����ɓw�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
4.2�C���^�r���[�̎p��
�C���^�r���[�ɂ����ẮA�b���肪�A�����ɓ��e�L�x�Ŋ���L���Șb�������Ă���邩����ł���B���̂��߂ɂ��A�C���^�r���[���J�n����O�ɁA���������̏����▼�O�𖾂����A�ԑg�̖ړI�ɂ��ė��������߁A�F�D�I�ɋ��͂��Ă��炦��悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ȊW���̍\�z�̂��߂ɐ����ȏ�̏������Ԃ����邱�Ƃ�����A���̏�ŗ��������߂ăC���^�r���[�����{���邱�Ƃ����邾�낤�B���̋͂��Ȏ��Ԃő���ɑ��āA�D��ۂ�^���A���͂��Ă��炤�W����z�����Ƃ��A�悢�C���^�r���[���s�������ł̏d�v�Ȕ\�͂ł���B����ۂƂ��ẴX�^�b�t��C���^�r���A�[�̑ԓx�╞���Ƃ��������̂��A�C���^�r���[�̐��ۂ����E����厖�ȗv�f�ł���B���Ζʂ̐l�Ɉ��A���ăC���^�r���[���˗�����Ƃ������Ƃ́A����Ȃ��ƋC���Ђ�����̂����A������������I��ǂ��������邱�Ƃ��C���^�r���[�̉ۑ�ł���A�P�����ׂ��\�͂Ȃ̂ł���B
�C���^�r���[���n�߂�ɍۂ��ẮA�u����ł́A��낵�����肢���܂��v�Ƃ��������A�ɑ����āA����⎩���̏Љ������ꍇ�����邵�A�����ɓ��e�ɂ͂����Ă������Ƃ����邾�낤�B�Θb�����Ă���ԁA������i�C���^�r���A�[�j�́A�b����̑��݂�F�߁A���t�������A���S���Ęb����i�߂Ă��炢�₷�����͋C�Â���ɐS���ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������́A���̑S�g�I�ȕ\���i���Ƃ�܂Ȃ����Ȃǁj��p���āA�b����̌��t���X�����Ă���ԓx�������A���邢�͑����E�C�Â��āA���̘b���𐨂��Â���������S���Ă���B��������Ęb���̓��e��c��܂��A�e�܂��āA���{���I�ȕ������o���w�͂�����̂ł���B
�������A������̑��Ƃ́A�u�͂��v�A�u�Ȃ�قǁv�Ȃǂ̌��t�Ƃ��Ă͔����Ȃ��ŁA�g�U���\����Ŏ����A�b����̌��t�ɕ�����̐����킳��Ȃ��悤�ɂ����ق����A�ԑg���ɍۂ��āi�ҏW��Ƃ̏ォ����j�ǂ����Ƃ������B���̂Ԃ�A���Ƃ����g�U���\��͂��傫�ȃA�N�V�����ƂȂ���̂ł���B
�C���^�r���[�ɂ���ẮA�b����̓s���Řb���Â炢���Ƃ�u�˂Ă݂������Ƃ����邪�A���̋삯�����́A�ԑg����̘g�g�݂�O��i�l�ԊW�Ȃǁj�ɂ���ēK�ۂ��l���čs���ق��Ȃ��B
�����Ȍ��t�K���Ƃ炦�đ����ǂ��l�߂�悤�ȉ����i�ꕔ�̃e���r�ԑg�Ɍ�����悤�ȁA�u�˂����݁v��u������v�Ƃ��������@�j�͏펯�I�ɂ͔�����ׂ����̂ł���B
�ԑg�C���^�r���[�ł́A��������b��������p�ȋْ������Ă������Ȃ���b�ɂȂ�Ȃ��悤�A���R�Ŋ���L���ȑΘb�������ł��镵�͋C�Â�����K�v�ł���B��萳�m�ɘb�����߂ɁA��{��p�ӂ����K���d�˂邱�Ƃ��悢�ꍇ�����邪�A�䎌���_�ǂݒ��ƂȂ��āA�V�N���⎩�R�������Ȃ��邱�Ƃ�����̂ŁA���܂胊�n�[�T���Ȃǂ͂����A�ł����킹�ɂȂ�����������邱�Ƃ��A���ʓI�ɂ͂悢�ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B
�C���^�r���[�����邱�Ƃɕs����ȏꍇ�́A���炩���ߗp�ӂ������⎖�������Ȃ������Ő���t�ƂȂ�A����̘b�����ǂ����������Ƃ��Ă��邩�A�����������ł���B�b���肪���܉�������ׂ낤�Ƃ��Ă���̂��ɏW�����A���̐S��ɂ��z�������Ȃ���A���̎����g�ݗ��ĂĂ������Ƃ����߂���B����̐S�ւ̑z���͂������ɓ������邩���A�C���^�r���[�̍ł��������ȉۑ�ł���Ɉӂł���Ƃ�����B
4.3�C���^�r���[�̌��t�ƓW�J
�ԑg�C���^�r���[�ɂ����ẮA���������������t���g�����Ƃ����߂���B������͐������h����g���i�܂��g���������j�A��b��\����L�x�ɂ��A���₪�P���Ȃ��̂ƂȂ�Ȃ��悤�ɋC�����āA�b����̑��l�ŕ��G�Ȍ��t���Ђ��������Ƃ��厖�ł���B
����̎�҂́A����ɑ��Ė��m�ȈӐ}��`���邱�Ƃ�B���Ƀ{�J���Ă��܂��悤�Ȍ��t�����Ŏ��₵�Ă��܂����Ƃ������B�Ⴆ�A
�@�@�@�u�E�E�E�Ƃ��H�v�u�E�E�E�������肵�܂��H�v
�Ȃǂ̌��t�����́A�ԑg�C���^�r���[�Ƃ��Ă͑Ó��ł͂Ȃ��B
�@�@�@�u�E�E�E�ł��傤��?�v�����Ƃ��l���ł����H�v�u�E�E�E�Ƃ������͂���܂��H�v
�ȂǁA����`�̌���𖾗Ăɔ�����ׂ��ł���B
�C���^�r���[�́A�A���P�[�g���Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����̓��������K�肵�Ă��܂��悤�Ȏ���A�Ⴆ�u�͂��v���u�������v�ł����������Ȃ��������͔�����悤�ɂ���B�Ⴆ�A���鉹�y�̃C�x���g�ŁA���ꂩ��X�e�[�W�ɂ����낤�Ƃ��Ă���Q���҂ɂ������āA
�u�{�Ԃ�O�ɋْ����Ă��܂��H�v
�Ƃ����������ɂ́A�u�͂��ْ����Ă��܂��v���u�����A����قǂł�����܂���v�Ƃ������P���ȓ������Ԃ��Ă��₷���B
�u�{�Ԃ�O�ɂ��č��̂��C���͂������ł����H�v
�u�����͂ǂ�ȃX�e�[�W�ɂ������Ǝv���Ă��܂����H�v
�Ƃ������A���������ɕ������������A�������ۓI�Ȍ��t�𓊂�������ق����A����̐S��ɂ��������l�Ȍ��t���Ђ������₷���B
�b����̉̂Ȃ��ŁA�s���m�ȂƂ����B���ȂƂ���́A�������Ƃ�ʂ̕�������������A���t�������Č����Ă��炤�H�v���K�v�Ȃ��Ƃ�����B�����莩�g�͒m���Ă��邱�Ƃł��A�����҂ɂ킩��Â炢�Ǝv���Ƃ���́A�Ղ������t�Ɍ��������Ă��������A������̌��t�ŕ₢�Ȃ��玿�₷��B
�u����́E�E�E�Ƃ����Ӗ��ł��傤���H�v�@�u����������E�E�E�Ƃ������Ƃł��傤���H�v�u�����ɂ��āA���������ڂ������b�������܂����H�v
�Ȃǂ̎�����d�˂���A������̑�����A�L�[���[�h��܂Ƃ߂̌��t���Ă݂�̂��A�悢���Ƃ�����B
�ҏW���O��ƂȂ��Ă���ꍇ�́A���炩���ߘb����ɂ������āA�u�������Ƃ����x�����Č��\�ł��B���̎��e�O�ɂ��������ʂ�f�Ƃ͐������Ȃ��ł��������B�v�ȂǂƗ���ł������Ƃ��悢�ꍇ������A��������S���āA�J��Ԃ����Ă���邱�Ƃ�����B�b����ɂ������A�J�����ɂ͎����������Ȃ��ŗ~�����ꍇ�ɂ́A���̂悤�Ɉ˗����Ă����Ƃ悢���Ƃ����邾�낤�B
�Ȃ��A�C���^�r���[�����l�́A�����̃C���^�r���[���ǂ̂悤�ɔԑg�Ɏg���邩�Ƃ������Ƃ��C�ɂ��Ă��邱�Ƃ����邵�A�ߑ�Ȋ��҂�����Ă���ꍇ�����蓾��B�ҏW�ɂ���ẮA�ԑg�̂Ȃ��ŁA�����Z���g������������A�g���Ȃ��ꍇ������Ƃ������Ƃ����O�ɓ`���Ă����������悢���낤�B���̓_�́A�����҂̃��f�B�A�ɑ��闝���̒��x�ɕ����ʂ����邪�A���݂��̐l�ԊW�̂Ȃ��ŁA�����Ɨ������K�v�ȓ_�ł���B
�\�Q�@���ȃC���^�r���[�̎���@�i���s�|�m�d�s�������q����̃C���^�r���[�̈ꕔ�j
|
�@�C���^�r���[�̏Ɖ�������̕\�� |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@��������̃C���^�r���[�̂��Ƃ@ ���P �u����ł͂�낵�����肢���܂��B�v ���Q �u�g���q�q�ǂ��X�e�[�V�����h�́A�������ĉ��N�ɂȂ�܂��ł��傤���H�v ���R �u���̑O����e�q����Ƃ��Ă���Ă���ꂽ�Ǝv���̂ł����A�g�[�^������Ɖ��N���炢�ɂȂ�ł��傤���H�v ���S �u����̐��́A���ł͉��l���炢�ł��傤���H�v ���T �u�������e�Ƃ��ẮA�ǂ�Ȃ��Ƃ��A��ɂ����Ȃ��Ă��܂����H�v ���U �u�ǂ��������v���ŁA���̎���~���[�W�J���Ƃ��������ɓ��݂�������ł��傤���H�v ���V �u���N�̃~���[�W�J���A������2��ڂ̗��K�������킯�ł�����ǂ��A2��ڂ��A�����ɂȂ��Ă݂āA�ǂ�Ȉ�ۂ��������ɂȂ�܂����ł��傤���H�v ���W �u�N����Ⴄ�q�ǂ��B���ꏏ�ɗ��K�����Ă���킯�ł����A�ǂ��������v�f����A�����������@���Ƃ肢����Ă���̂ł��傤���H ���X �u�����������l�ł��Ƃ��A����l�����l�������������Ă܂������A���Ђ���ȗl�q�����Ē������炢���ł��ˁB�v ��10 �u���ꂩ��1���܂ł̊����̒��ŁA�q�ǂ��B���ꂼ����A���낢��ڕW�������Ă�Ǝv����ł�����ǂ��A�g�q�ǂ��X�e�[�V�����h����Ƃ��ẮA�ǂ������Ƃ������Ԑg�ɂ��Ă����ė~�����ȂƁA�v�����ł��傤���H�v ��11 �u�n�悮��݂ŁA�q�ǂ��B���݂�Ƃ������Ƃł��傤���H�v ��12 �u����~���[�W�J�������łȂ��āA���̒��̎q���������A�ǂ�ȑ�l�ɁA�����������Ă����ė~�����Ȃ��āA����Ă��ł��傤���H�v ��13 �u����������l�ɂȂ��Ă��炤���߂ɂ��A�g���q�q�ǂ��X�e�[�V�����h����Ƃ��ẮA���ꂩ��A�ǂ�ȕ������������ł����H�v ��14 �u�q�ǂ���������Ȃ��āA��l�݂̂Ȃ�����ꏏ�ɐ������Ă�����Ƃ������Ă������Ƃł��傤���H�v ��15 �u�܂��܂����ꂩ��A��������҂��Ă���܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂����B�v |
||||||
���ȃC���^�r���[�̎��ۗ�Ƃ��āA���s�|�m�d�s�̉������q���A���Ђ̃C���^�[�l�b�g�e���r�i�r�s�`�c�|�s�u�j�̎�ނł����Ȃ����C���^�r���[�ɂ��ĕ\�Q�Ɏ����B���̏�ʂŁA�������A�q�������ɂ�����~���[�W�J�����w�����Ă���NPO�̃����o�[�ɃC���^�r���[���Ă���B
��������́A�����ǂ̌��A�i�E���T�[���������Ƃ�����A���������������t�����┭�������Ă��邱�Ƃ͂������A�b����̌��t�ɑ��āA�傫����������A����A����L���ɑf�����������Ă��邱�Ƃ���������悤�B�b����̌��t�������V���A�X�ȓ��e�ɐG�ꂽ�Ƃ��́A�^���ȕ\��������A�y�����b�ɂ͖��ʂ݂̏��ׂ�B���̂悤�ȃC���^�r���A�[�ׂ̍₩�Ȕ����́A�b��������S�����A�E�C�Â��A�����Â��Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B����ł��āA�u�͂��v�u�Ȃ�قǁv�Ȃǂ̌��t���Ă��炸�A�b����̌��t�Ɖ������d�Ȃ��Ă��Ȃ��B
�C���^�r���[�̍ŏ��̂ق��ł́A���Q�u�������ĉ��N�ɂȂ�܂��ł��傤���H�v�A���S�u����̐��́A���ł͉��l���炢�ł��傤���H�v�ȂǂƋ�̓I�ȓ_��u�ˁA����ɁA���U�u�ǂ��������v���ŁE�E�E�v�A���V�u�ǂ�Ȉ�ۂ��������ɁE�E�E�v�Ȃǂ́A�l�ԓI�Ȏv���⊴�o�Ƃ��������̂ɃE�G�C�g���ڂ��Ă����Ă���B
�C���^�r���[�̒��Ոȍ~�ł́A��11 �u�n�悮��݂ŁA�q�ǂ��B���݂�Ƃ������Ƃł��傤���H�v�A��13 �u���ꂩ��A�ǂ�ȕ������������ł����H�v�A�ȂǂƁA�b����̌��t��������A����ʐ��⒊�ې��̍������e�ɂ��Đu�˂Ă���B
�Ō�ɁA��14 �u�q�ǂ������ł͂Ȃ��āA��l�݂̂Ȃ�����ꏏ�ɐ������Ă�����Ƃ����Ƃ������Ƃł��傤���H�v�ƁA�Љ�I�ŕ��Ր��̂���L�[���[�h����������̕����瓊�������邱�ƂŁA���̊����̈Ӌ`���̗g���A��15 �u�܂��܂����ꂩ��A��������҂��Ă���܂��B�v�Ƙb����ւ̃G�[�����āA����₩���C���^�r���[���܂Ƃ߂Ă���B
�C���^�r���[�̗��_�ƕ��@�ɉ������A����{�ƂȂ�Ⴞ�Ƃ����悤�B
4.4�ԑg�C���^�r���[�̌��J�E�ۑ����̗��ӓ_
�ԑg�C���^�r���[���s���ɍۂ��ẮA��ʓI�Ȏ����҂̗ǎ���펯��z�肵�A�����ȕ\���ɂƂ߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ق��̐l�̗��ꂩ��͍�����肪�����邱�Ƃ����O���ꂽ��A�v���C�o�V�[�Ɋւ����ɂ��ẮA���ɐT�d�������߂���B
�ԑg�̌��J�ɂ��ẮA��{�I�ɂ́A�b���肪���O�ɗ������Ă��邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A�����ԑg�����łȂ��A�C���^�r���[���L�^�����f�ށi�r�f�I�e�[�v�j�ɂ��Ă��K�ɕۊǂ��A�s�p�ӂɊO���ɗ��o���đ�O�҂̖ڂɐG���悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤���ӂ���B�A�}�`���A�ł����Ă��A���̎Љ�I�ӔC�͕����Ă���̂ł���B
�C���^�r���[�͕�����Ƙb����Ƃ̂����̑Ό��Ƃ����Ȃ����Ȃ����A�f�B�x�[�g�i���_�j�������Ȃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���������������Ă���킯�ł��Ȃ��B������̑����u�����̎p���ǂ��f���Ă��邩�v�ɋC���Ƃ��Ă��肢�Ă͂����Ȃ��B
�C���^�r���[�ɋ��͂��Ă����l�����ɑ��ẮA�ǂ̂悤�ȏꍇ�ł����h�Ɗ��ӂ̔O�������Đڂ���ׂ��ł���B���ʓI�ɁA�悢�C���^�r���[�������Ȃ�����Ƃ����āA�b������Ȃ߂�悤�ȑԓx�́i���̐l�̑O�ł͂������A���Ȃ��Ƃ���ł����Ă��j�T�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�b����ւ̊��ӂ̔O�����������Ȃ�������̎p�́A�����҂�������ꂵ�����̂ƂȂ�B
���܂��܂ȏ�����z�����s���Ă��A�C���^�r���[�������̖ړI��B���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͂��蓾��B�Z�p�I�Ȗ��n����A�v�̂Ȃ��ԓ��Ȃǂ�����̂ŁA�ԑg����S�̂̂Ȃ��őΉ�����������ق��Ȃ��B������i���b����̊��҂����Ă��Ȃ��ꍇ�����邵�A����ɂȂ��Ă��甭���̓P����蒼�������߂��āA�C�����K�v�ƂȂ邱�Ƃ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B
���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�C���^�r���[�ɂ͂��܂��܂ȓ�������邪�A��{�I�ɂ͔ԑg�̍���i������j�̐��ӂƐ^���Ȏp�����A��ޑΏۂ̑��i�b����j�ɓ`���A��������Ă���A�����đ傫�Ȗ��͐����Ȃ��͂��ł���B�悢�ԑg���������邱�ƂɁA�b����ƕ�����̖ړI���т����L�ł���悤�ȏ�݂��Ă������ƂŁA���̉ߒ��ɂ����Ă��A���ʂɂ����Ă��A���݂��Ɏ���̂���C���^�r���[�Ƃ��Ă������Ƃ��\�ƂȂ�ł��낤�B
�T.�Љ�I�Θb�Ƃ��Ă̔ԑg�C���^�r���[
�悢�C���^�r���[���s�����߂ɂ́A�����܂łɏq�ׂĂ������_�𗝉����������ŁA�P���ƌo����ς�ł����ƂƂ��ɁA�D�ꂽ��i��A���ȃC���^�r���[�̗���悭�ςĂ������Ƃ����������B�����̃C���^�r���[�Ɣ�r���Ă݂邱�ƂŁA�l�I�Ȃ�����ׂ�Ƃ͈قȂ�A�v���̃C���^�r���A�[�̑Θb�\�͂̍����A�Љ�Ɍ����Č��J������b��Βk�̐�����m���Ă����ׂ��ł���B�C���^�r���[�����鑤�i�b����j���A�鑤�i�b����j���A���̌o����ʂ��āA�݂��𗝉����A���������߂Ȃ����A�Ƃ��ɐ����ł���悤�ȁA�C���^�r���[�����邱�Ƃ��ڕW�ƂȂ邾�낤�B
�悢�ԑg�C���^�r���[�͂��₷�����Ƃł͂Ȃ����A�ԑg�ɐl�ԓI�ȓ��t�����������邤���ő傫�Ȍ��ʂ�������̂ł���A�L���ȃR�~���j�P�[�V�����\�͂��琬���Ă������߂ɂ��A�ϋɉʊ��Ƀ`�������W���Ă������l�̂�����̂ł���B�����Ă��̐��ʁi�ԑg�j���Љ�Ɍ��J���Ă������ƂŁA����ɖ�����Ă������ƂƂȂ邾�낤�B���̂悤�ȏ�M������ςݏd�˂Ă������Ƃ́A�������̎Љ�A�Θb�Ƒ��ݗ����̂��߂ɓw�͂��������Ƃɉ��l�������A���L���Ől�ԓI�ȎЉ�̐��n�ɂނ��āA�������ɖ𗧂ɈႢ�Ȃ��B
�Љ�I�Θb�͂́A�����Đ����̔\�͂ł͂Ȃ��A�ӎ������P�����邱�Ƃň琬�������̂ł���A�N�ǁE�X�s�[�`�E���A�E�����ȂǁA�������ŁA�_���I�ɁA���X�ƁA�p���悭�b�����ƁA�����Ă��܂��܂Ȑl�X�Ƃ̊y�������t�̃L���b�`�{�[�����ł���悤�ɂȂ��āA����̐l����L���Ȃ��̂Ƃł���悤�ɓw�߂Ă����ׂ��ł���B
�ԑg�C���^�r���[���˗����Ă��A�����������R���Ȃ��f��l�ⓦ���o���l������B���̂悤�ȐS��͗��������ׂ������A�����ۂ��ŁA�������C���^�r���[�����߂�ꂽ�Ƃ��ɁA���ł������̍l����咣��K�A�Ȍ��ɃR�����g���邱�Ƃ��ł���悤�ɁA������P�����Ă������Ƃ͑�Ȃ��Ƃł���B
���ۂɃC���^�r���[�����ʂ������Ă��Ȃ��Ă��A���i���玩���̍l�������܂Ƃ߂āi���ꉻ�A���ۉ����āj��������A�����b�̂Ȃ��ł��A���悢����\���ɐS���ӂ��Ă������Ƃ��K�v�ł���B�����Ĕԑg�C���^�r���[������闧��ɂȂ�����A���X�Ǝ����ł���悤�ł��肽�����̂ł���B
����Ɍ����Ȃ�A�����̕��f�̊������A�Љ�ɑ��Ăǂ̂悤�ɕ\�����������邩����ɍl���Ă������ƁA�����ɂ͈�ʓI�ȕ��Ր���Љ�I�Ӌ`������̂��A����ᖡ���āA�Ȃ݂��肵�āA���̎p�𐳂��Ă����Ƃ����p�����A�l�Ԃɂ͋��߂��Ă���B����́A���ۂ̃��f�B�A�ɂ��C���^�r���[�ł͂Ȃ��A���炪����ɂ����Ȃ��C���^�r���[�i���ʊώ@�j�ł��邪�A���ۂ̔ԑg�C���^�r���[�ŕ�����Ƙb���肪���z���Ă��鎋���҂̑��݁A���Ȃ킿�Љ�I���L�T�O�i�O�����h�X�g�[���[�j�Ƃ������̂́A���̂悤�ȓ��ȓI��ʂɂ����Ă��L���ɋ@�\����ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�C���^�r���[�����邽�߂ɁA�����ǂ������̂��Ƃ������Ƃ��l���A��������H���d�˂�Ƃ������Ƃ́A�������C���^�r���[���ꂽ���ɂ͂ǂ�������̂��Ƃ������Ƃ��l���邱�ƂɂȂ����Ă���̂ł����āA�����Ƃ͂Ȃɂ����l����͂����{���Ă���͂��Ȃ̂ł���B
�ȏ�̂悤�ȍl�@�ɂ���āA��1�ɁA�ԑg�C���^�r���[�́A�ԑg�S�̂ɐl�ԓI�ȓ��t���□�킢�A�[����^����L���Ȏ�@�ł��邱�ƁA��2�ɁA�ԑg�C���^�r���[�́A������Ƙb����A�ԑg�̍���Ǝ����ҁA�ǂ̗���̎҂ɂƂ��Ă��A���҂̐S�̂Ȃ��ւ̑z���͂��͂��炩���A����̎p�����Ɏʂ��Č��������Ƃ��ł���D�ꂽ�w�K�̌��ƂȂ邱�ƁA��R�ɁA�ԑg�C���^�r���[�ɂނ��āA���܂��܂Ȗⓚ��z�肷���ƂȂǂ�ʂ��āA���玩�⎩������͂�����Ă����͂��炭�ނ��Ƃɂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��w�E����悤�B
�����ʂɂ������w���҂́A���̂悤�Ȕԑg�C���^�r���[�̈Ӌ`�ƕ��@�ɂ��Ă悭�������A���̊w�K�@��̑n�o�ɓw�͂��邱�Ƃ����߂���ł��낤�B
�Q�l����
����ג��w�e���r�̉R�����j��x�V���V���i2004�N10���j
���c�������w�h�L�������^���[��Ƃ̎d�� ���A���e�B��T��!�x�t�B�����A�[�g�Ёi2004�N12���j
�ɓ��q�N�@�u�ԑg�C���^�r���[�̋���I�Ӌ`�v�@��t�������w�Z���猤������o������I�v�@��38��pp.8-11�C2005�N5��